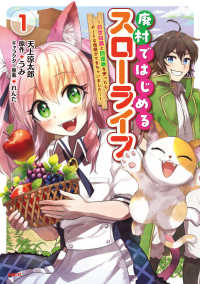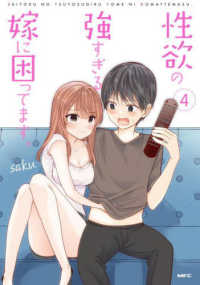内容説明
1972年10月、雪深い南米アンデス山脈に45人の乗客を乗せた旅客機が墜落した。奇跡的に32人が死をまぬがれたが、彼らを待ち受けていたのは極寒と飢餓の絶望的な状況であった。捜索が打ち切られ、食糧が底を突いたなか、彼らは死者の肉を口にして生き続けることを決断する。そしてふたりが標高4000メートル級の雪山を越えて脱出に成功、救助隊を遭難現場へと導いた。そのひとり、ナンド・パラードが、35年の時を経て初めて語る真実とは…。
目次
1 事故が起こるまで
2 何もかも貴重品
3 約束
4 もうひと息分だけ生きよう
5 見捨てられてもなお
6 アルミの墓場
7 東へ
8 死の向こう側
9 人を見た…
10 その後
著者等紹介
海津正彦[カイツマサヒコ]
1945年、八王子市生まれ。早稲田大学政経学部卒業。翻訳家。学生時代から登山に親しみ、ヒマラヤ初登頂の経験もある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
みゆき
23
旅行を兼ねたラグビーの親善試合のためチリへ向かった飛行機が、アンデス山中に墜落。救助が打ち切られた極寒の中、72日間も耐えた生還者がいた。彼らはただ手をこまねいて救助を待っていたのではない。それがこの実話の物凄さ。強靭な体力と精神力を支えたものは、死生観や宗教観か?死を選んだ方がずっと楽なのに、何故生きて帰らなけばいけないのか?第10章「その後」と「エピローグ」にその答えがあった。全ては愛のために。山越えの凄まじさは、読んでるだけで呼吸が止まりそうだった。2024/03/22
gtn
17
それを食するのも、食さず死を選ぶのも破戒。生存者はそれに口を付けることを選択する。そこから宗教心というベールを取り除けば、本能が残る。2019/03/17
bouhito
6
サッカークラブの飛行機事故が記憶に新しいが、これは1972年に起きたウルグアイのラグビーチームを乗せた飛行機の墜落事故だ。彼らには冬山への供えがないどころか、故郷のウルグアイには高い山がなく、登山というのもまるで初体験だった。45人中29人が亡くなった。16名が生き残ったとも言える。それも、72日間かけて…である。彼らは、亡くなった者の肉を食べることで飢えを凌いだ。それは正しい行為だったのか?究極の状況において、人間は善悪を越えた行為を求められる気がした。2016/12/17
sasha
5
雪に覆われたアンデス山中に墜落した航空機。捜索活動は打ち切られた。ならば、自ら助けを求めに行くしかない。体力は衰え、飢えと渇きに苦しみ、雪山登山の為の装備などない。それでも生きて還る為に、10日をかけてチリの山小屋へ辿り着く。ありえないわ、自分なら絶対に雪に埋もれて死ぬことを選んでるわ。あまりも過酷な極限状態を生き抜いた人たちには、ただただ驚嘆する。2015/02/04
Misae
4
P.P.リード「生存者」に続いてこちらも読んでみた。 生存者の一人、ナンド・パラードによる事故の記録。 主にナンドの心の内が描かれている。「生存者」を読んだばかりだったので、話の流れはわかっていたが、その時々ナンドの揺れ動く心情が激しく描かれていた。絶望したり何としても生きるのだと父に誓ったり。 共著者であるヴィンス・ラウスのあとがきにあるように、この本を通してナンドの眼球を通してアンデスを見つめ、読者を雪山に閉じ込められ恐怖を切り抜けるという体験をした。2024/10/16