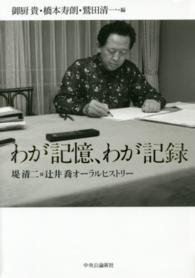内容説明
動物文学の第一人者・戸川幸夫が昭和20~30年代に秋田県の阿仁マタギに密着したノンフィクション作品を文庫化。マタギたちとともに雪深い山に入って狩猟の現場を取材し、往時の集落を訪れて衣食住や風習、マタギのルーツなどを精緻な文章と豊富な写真で記録した。マタギのシカリ(頭領)の家に代々伝わっていた『山達根本之巻』の原文も収録。
目次
狩座にて(マタギを追って;クマの行動;シロビレタタケ)
マタギの里(最後のマタギ村;根子紀行;村の移ろい)
マタギ風土記(始祖万事万三郎;山神さま;マタギ組;山達作法;当世マタギ;名うてのマタギ)
村の歳時記(行事・祭事;村のしきたり)
鷹匠―ひとりマタギ(名鷹匠・沓沢朝治;吹雪と老人)
著者等紹介
戸川幸夫[トガワユキオ]
1912年、佐賀県佐賀市生まれ。動物文学作家。旧制山形高校出身。東京日日新聞(現毎日新聞)社会部記者を経て、文筆活動に入る。1954年、『高安犬(こうやすいぬ)物語』で第32回直木賞受賞。1965年、沖縄・西表島でイリオモテヤマネコを発見。1978年、第28回芸術選奨受賞。2004年5月、逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
booklight
26
小さいころ動物小説でお世話になった戸川幸夫のマタギルポ。昭和20~30年ごろの秋田や岩手に実在したマタギたち。雪崩が起きるから豆はふもとでも炒らないとか、忌語をしゃべったら雪で禊をするとか色々大変。他の猟師から「俺たちはマタギみたいにめんどくさいことはしない」ともいわれるぐらい。でも科学的知識がない中で、しきたりとしての知恵の伝承が必要だったのだろう。卓越した技術と日本では珍しい猟生活の記録が面白い。よく考えたら熊追い猟とか怖いし奇妙な猟だ。矢口高雄が描いたマタギ像から一歩踏み込んだ実像がわかった。2024/04/27
mahiro
17
著者の戸川幸夫氏の名も懐かしい、昭和20〜30年代に東北のマタギと共に山に入ったり集落を取材時した記録。マタギは当時でも伝統や戒律が消える最後の世代だった。写真なども比較的に多く載っており阿仁地区の奥深い村に残っていた祭りや茅葺きの家や山入りするマタギの装いなどが良く分かった。又マタギよりもっと知らなかった鷹匠の事にも触れられており、迫力ある狩りの仕方やや鷹との深い絆が描かれていた、クマタカは狐や狸も仕留めるのか…2023/02/09
DEE
10
渋い本を読んでしまった。 鉄砲を持ち独特の衣装を着て山に入るマタギ。この本が書かれた40年近く前においても本職のマタギはすでに居なかった。 そんな消えつつあるマタギの世界を、実際のマタギたちからの話と、自らも狩りに同行した経験に基づき書き記したのがこの本。 マタギ=猟師ではないんだな。 白黒写真も多数掲載されているけど、当時の東北の山の中の暮らしぶりを知れる貴重なものだと思う。2021/11/11
スプリント
6
マタギの生活を知るためにフィールドワークを行った記録です。知られざる生活が伝聞だけでなく著者の経験に基づき書かれているのでとても興味深い内容だった。2021/12/23
ぼぶたろう
5
あの戸川幸夫が書いたマタギのルポだと‥?!と、阿仁の旅館の売店で衝動買いしました。笑 「邂逅の森」が好きすぎて、その理解を深めるのにとても役立ちました。また、戸川さん目線のマタギの描写がとってもいい。戸川さんご自身のマタギへのリスペクトも感じられた。おごそかで、たくましくて、どこか滑稽なマタギたちとその文化は令和の今でも私たちを魅了する。2025/12/02
-

- 電子書籍
- 狂戦士なモブ、無自覚に本編を破壊する(…