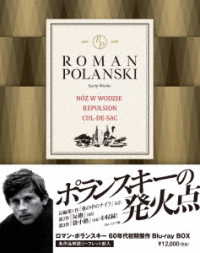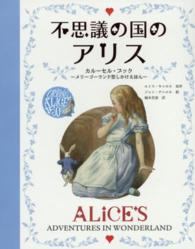内容説明
極寒の地アラスカで繰り広げられる生きものたちの営み。トウヒ、アカリス、ハタネズミ、オオカミ、カリブー、ムース、インディアン、白人猟師―それぞれの物語が縦横に絡み合い、重なり合い、命が交差する瞬間を、詩情豊かな筆致で捉えた自然文学の傑作。写真家、故星野道夫の愛読書であり、気候危機、生物多様性危機の時代の必読書。
目次
プロローグ
旅をする木
タイガの番人
ハタネズミの世界
ノウサギの世界
待ち伏せの名手
狩りの王者
カリブーの一年
ムースの一年
ムースの民
生命は続く
ホームステッド
にわか景気
未来の展望
著者等紹介
プルーイット,ウィリアム[プルーイット,ウィリアム] [Pruitt,Jr.,William O.]
1922‐2009。動物学者。アメリカのメリーランド州生まれ。アラスカにおけるアメリカの核実験場開発計画「プロジェクト・チャリオット」を環境調査によって阻止し、そのためアメリカを追われることになった。その詳細は星野道夫著『ノーザンライツ』に記されている。カナダに移住後は、マニトバ大学動物学研究室教授。タイガ生物学研究所を設立。極寒地における野生生物の研究を続け、カナダ科学アカデミー最優秀賞などを受賞。93年、アラスカ州政府より正式の謝罪を受け、名誉回復。アラスカ大学名誉博士となる
岩本正恵[イワモトマサエ]
翻訳家。1964年東京生まれ。東京外国語大学英米語学科卒業。2014年逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
帽子を編みます
65
極寒の地アラスカの生きものたちの暮らし、旅をする木トウヒから始まり、動物たち、そして人間に未来に次々に繋がっていきます。アピ、プカック(雪の状態)、カマニック、クウェリなど専門用語が馴染みにくいですが、硬質ながら繊細な筆致に生命の輝きを感じます。広がる大自然が繊細なバランスで成り立っていること、わずかな乱れで容易に崩壊すること、回復にかかる時間の長さ。なぜ我々は学ばないのか…。正確で繊細なイラストもイメージを膨らませてくれます。書かれたときから50年以上たっていますが古びることなく示唆に富んだ一冊です。2022/03/10
piro
46
星野道夫さんの愛読書だったという本書。アラスカ・カナダのツンドラ・タイガに生きる動物達の生態だけでなく、それらが絶妙なバランスの上で成り立っている脆弱な生態系である事を知らしめてくれる良書です。長い時間をかけてその生態系の一部になり得た「ムースの民」アサバスカインディアン・ディンジェ族の様な知恵と感覚がない限り、この生態系を維持する事は難しいのだろうな。これは極北だけの話ではなく地球上に生きる全ての人々に課された宿題だと感じました。今年文庫として復刊された日本語版、今この本を読む事ができて良かった。2022/08/15
@nk
44
知ることではなく分かることが全てのはじまりならば、本書を読み、将来を改めて案じ、できることを探しながら暮らすことが読者の定のようにさえ感じた。/プロジェクト・チェリオット(アラスカでの核実験場設置計画)に対し、生態系への影響により中止を訴えたのが本著者。しかし彼の報告書は改竄され、研究に勤しんでいた大学からも追われる。その後に執筆したのが本書であり、1967年に米国で刊行、絶版を経て2度の再刊。日本では2002年に翻訳版、そして20年後の今年、漸く文庫版となった。⇒2022/05/31
おせきはん
34
アラスカの大自然で生きる動物や人間の営みを紹介しています。それぞれが生態系の中で各々の役割を果たしている一方で、一部の人間により、その絶妙なバランスがいとも簡単に崩されてしまうことが、臨場感あふれる文章から伝わってきました。2022/12/26
やま
27
東京都写真美術館で星野道夫展があると聞き、たまたま時間が空いたので行った。もちろん、その膨大な、そして1枚1枚が物語を生んでいる写真にも圧倒されたのだが、星野氏が愛読していたというこの本が文庫版として発売されていて、思わず手に取った。◇星野氏は30代でカムチャッカ半島でヒグマに襲われて亡くなられた写真家で極北の生物も大学で学んだという経歴を持つ。この本を読んでいると、その語り口は星野氏のいろんな本へ影響を与えていることがわかる。まるで目の前にその生物がいるような錯覚を覚えるほどリアリティにあふれている。→2023/01/02
-

- 電子書籍
- たっちゃん、どっちとる?【分冊版】 2…