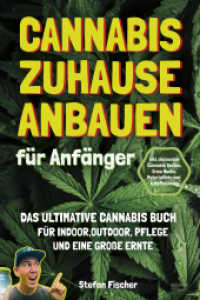内容説明
アリの巣を観察すると、いつも働いているアリがいる一方でほとんど働かないアリもいる。働かないアリが存在するのはなぜなのか?ムシの社会で行われる協力、裏切り、出し抜き、悲喜こもごも―。コロニーと呼ばれる集団をつくり階層社会を営む「真社会性生物」の驚きの生態を、進化生物学者がヒトの社会にたとえながらわかりやすく、深く、面白く語る。ベストセラーの復刊文庫化。
目次
序章 ヒトの社会、ムシの社会
第1章 7割のアリは休んでる
第2章 働かないアリはなぜ存在するのか?
第3章 なんで他人のために働くの?
第4章 自分がよければ
第5章 「群れ」か「個」か、それが問題だ
終章 その進化はなんのため?
著者等紹介
長谷川英祐[ハセガワエイスケ]
進化生物学者。北海道大学大学院農学研究院准教授。動物生態学研究室所属。1961年生まれ。大学時代から社会性昆虫を研究。卒業後、民間企業に5年間勤務したのち、東京都立大学大学院で生態学を学ぶ。主な研究分野は社会性の進化や、集団を作る動物の行動など。特に働かないハタラキアリの研究は大きく注目を集めた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きみたけ
56
面白かった☺著者は北海道大学大学院農学研究院准教授で進化生物学者の長谷川英祐先生。アリやハチなどの社会性生物の様々な生態を紹介し、その奇妙でときにユーモラスな行動を読んで楽しめる一冊。2016年6月発刊「働かないアリに意義がある」をベースに改訂。ムシの集団行動の例とワーカーの働き方、ワーカーの個性の違い、そしてどのような作用で働くのか、集団で生き延びていくことの重要性など解説。7割の働かないアリを抱えてもいざという時は全員で力を発揮するそうです。そんなゆとりのある会社で働きたいですな〜😑2025/11/13
ゆう
17
社会の中に余力を持つことは、短期的には単なる無駄や非効率に思える。しかし、長期的な視点では余力を備えていることが、変動性やランダム性から利益を得ることに繋がり、全体の存続に有利に働く。陳腐な感想だが、自然や生物が持つメカニズムには、まるで誰かが作ったかのような知性を感じる。生存し続けるためには、頑健性よりも反脆弱性が重要だということを、自然は人間よりもよく理解している。2024/06/23
しょうご
12
「ほぼ日の學校」でお話しされていたのをきっかけに興味が湧き購入しました。 アリのコロニーには働きアリがいる一方で働かないものもいるそうです。 ちなみに働かないアリを集めるとこの中でも働くアリとそうでないアリに分かれるとのことでした。 汚い部屋にいて掃除をしようと思うタイミングが人それぞれ違うという表現に納得しました。 学問や研究って本来こういうものなのだという気概のようなものを感じとることができました。2021/09/14
しみー
10
普通に面白かった。組織としてみんなが働くヤツより働かないヤツがいないと成り立たない。そしてそういうヤツが思いもかけない近道を見つけたりする。2023/05/22
ニャンリッチ
9
生物は働けば必ず疲れる。全員が疲れるとコロニーは壊滅する。仕事に対する反応閾値(腰の軽さ)が個体によって異なる=働かない個体が出てくるのは、コロニー全体としてのいざというときの冗長性ということか。今即効で役立つことや、瞬間的な効率の最大化ばかり求める現代日本に警鐘を鳴らす。私が勤め先で担当してる無駄としか思えない事業も、別の事業に応用できる日が来るのかもしれないと思うことにしよう。/専門的な研究内容をかなり噛み砕いてくれていることはわかるが、それでも難解な文章がたくさん出てきて挫折しそうになった。2024/05/18
-

- 洋書
- ALIAS ADAM