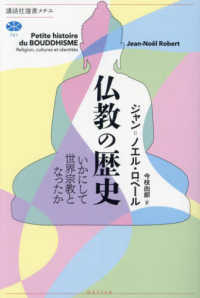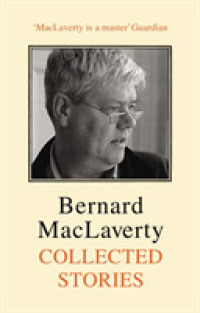出版社内容情報
『定本 日本の秘境』『旅に出る日』に続く岡田喜秋氏の紀行文復刊第三弾!
内容説明
都市近郊の低山から奥山の懐深くまで、ときに深い森をぬけ、ときに日本アルプスの高峰を仰ぎつつ、山とともに人々が暮らす風景を訪ねる…。旅行雑誌『旅』の名編集長として知られた著者が、歩いて旅した日本全国の山里のようすを精緻に記録した紀行文三十二編を収録。一九七四年に初版が刊行された際は大きな反響があった名作を復刻し、未来に伝えたい山村の風景を再現する。
目次
第1部 山村の組曲(秩父の隠れ里へ;こけしの里の鎮魂歌;冬野―中世の飛鳥路 ほか)
第2部 アルプスの見える村(冬枯れの湖畔;甲斐駒が見守る温泉宿;空狭き谷間 ほか)
第3部 推理する山旅(祖谷溪の源平譚;柳久保池と奇蹟の民家;秋葉街道・三泊四日 ほか)
著者等紹介
岡田喜秋[オカダキシュウ]
1926(大正15)年、東京生まれ。作家。旧制松本高校を経て、1947(昭和22)年、東北大学経済学部卒業。日本交通公社に入社し、1959(昭和34)年より十二年間、雑誌『旅』の編集長を務める。編集者時代から日本各地を取材して、数多くの紀行文を発表。退職後は、横浜商科大学教授として、観光学の構築に努める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やいっち
63
現下の外出自粛の状況に鑑み、敢えて旅の本を書庫から選んできた。歴史や、あるいは歴史にならない人々の生活や足跡が残っているはずの山村の道。時に敢えて道なき道を選ぶ著者の姿勢に共感。紀行文というと、何と言ってもイザベラ・バードである。彼女は往時の日本人の生活の中に深く立ち入っていく。2020/05/26
HANA
48
日本のそこかしこに点在する山里。本書は山里をひたすら歩いた記憶である。主に日本アルプス周辺が主となっているが、それでも東北や四国等その足跡は幅広い。読んでいる最中思ったのは、どんな村にもそこに住んで暮らした人の記憶が沈み込んでいるという事。平家の落人伝説等だけではなく、そこに暮らしていた人の記憶みたいなものが文脈のそこかしこから感じられるようであった。本書が書かれたのは半世紀の昔、今現在山村を歩く本が書かれたらどうなるんだろうなあ。ともあれ晴れた日に野や山をそこはかとなく歩きたくなる、そんな一冊でした。2016/05/27
Akihiro Nishio
22
Amazonのメールで紀行文学の名作と紹介されていたので購入。山村を歩くというタイトルだが、筆者は登山やハイキング畑の人で、宮本常一的な著作を求めていた自分としては期待はずれ。風景の描写に優れ、特に山を語る時には熱がこもる。自分には、どうして山を様々な角度から見て、こうも惚れ惚れできるのかさっぱりわからない。ロマンチックな風景描写に、歴史的な出来事も重ね合わせて、それなりに読ませるが、やはり宮本と比較すると物足りなく感じる。ジャンルが違うとはわかってはいるのだが。登山家がロマンチストだということを知った。2017/09/05
やいっち
9
期せずして、我が母校の先輩の本を相次いで読んできた。一冊は本書であり、もう一冊は藤井一至著の「大地の五億年 せめぎあう土と生き物たち」である。特に藤井氏は富山県の人。それはともかく、母校のある仙台の街に新旧こうした尊敬すべき人がいることに感激。岡田喜秋氏は、東京の下町生まれだが、山に惹かれて高校も旧制の松本高校を選んだとか。山間の忘れられた、あるいは消えていった村々やあるかなきかの山道、峠道を歩いて回った。 2016/05/23
sashi_mono
8
『定本 日本の秘境』の続編ともいうべき、昭和40年代の山村を訪ね歩いた紀行文集。高度経済成長の道路開発と観光化により各地に人波が押し寄せる時世下にあって、著者は往時のすがたを求めて人影少ない山里へと足をむける。家屋の建築様式に平家の落人伝説を嗅ぎ、日本人の心性にふれる唱歌「ふるさと」の実景を突きとめ、馬子が往来した街道の挽歌に耳をそばだてる。本を開くと、旅情にさそわれ、人知れない山里へとふらりと出掛けたくなった。2018/01/24