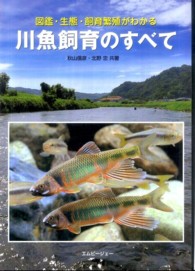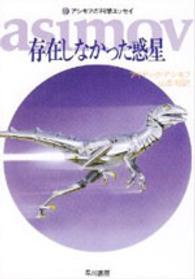内容説明
山を舞台に多くの傑作を生み出した作家・新田次郎の、四季の自然と山を綴った随筆と、小説の素材ともなった山岳紀行を再編。多感な少年時代を過ごし、自然観の原点となった霧ヶ峰の自然、厳しい自然と向き合った富士山測候所勤務の経験など味わい深いエッセイと、飾らぬ筆致で作家の山旅姿が浮かび上がるような紀行。
目次
随筆1―『白い野帳』より(冬;春;夏 ほか)
紀行―『山旅ノート』より(魚津と立山;知られざる山;秋の南アルプス ほか)
随筆2―『山旅ノート』より(日本アルプスの旅;失われた故郷;ブロッケンの妖異 ほか)
著者等紹介
新田次郎[ニッタジロウ]
1912年、長野県諏訪郡上諏訪町(現諏訪市)に生まれる。本名藤原寛人。旧制諏訪中学校、無線電信講習所を卒業後、1932年、中央気象台(現気象庁)に入庁。1935年、電機学校卒業。富士山気象レーダー(1965年運用開始)の建設責任者を務めたことで知られる。1956年『強力伝』で、第34回直木賞受賞。1966年、気象庁を退職し、文筆に専念。1974年、『武田信玄』ならびに一連の山岳小説に対して吉川英治文学賞受賞。1979年、紫綬褒章受章。1980年、心筋梗塞のため逝去。正五位勲四等旭日小綬章(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ろこぽん
10
新田次郎さんのエッセイ初めて読んだ。新田次郎好きだわー、彼の文章も結構わがままで我が強くて、時には悪口(?)のようなことをエッセイに書いてしまうことも全部含めて。 彼は登山人気に比例し、山に人が入り自然が破壊されることをエッセイの中でたびたび嘆いておられるけれど、私は同時に山に憧れ、山を愛する人も増えていると思っています。2020/02/12
hitsuji023
10
新田次郎の随筆集。自然や山について素直に見たまま感じたまま書かれている。登山家ではないとのことで、山登りするときのマイペースな遅足が気に入った。自分も周囲に過度に合わせることなくマイペースで歩きたい。コブシの花が好きだとか(作中何度も出てくる)、登山中道に迷ったり、子供時代の話、ブロッケン現象などなどエピソードが面白い。時間を置いて何度でも読めそうだ。2015/12/08
キムチ
10
「朝日新聞」の夕刊掲載のエッセイを中心に「旅」「山と渓谷」掲載の紀行文、随想をまとめたモノがよみがえった。仲間から、「ヤマケイ文庫」の存在を聞き、早速読む。新田氏は誰しもが認める山岳作家だろうが登山家ではない。だが故郷を深く愛し、山を愛し、多くの山に踏み入っている。春夏秋冬の姿、花、動物たち・・ 登場する舞台は昭和40年代までだが、当時から山の俗化、自然荒廃を憂えている。 当時より遥か進んだ今日のそれを感じつつ、やっぱ「山はええなぁ~~」 情けなくもヘロヘロ歩いたアルプス連山を想い、また今年も!2013/04/14
ふーてー
8
雷の話、山が荒れていくお話、一見つい最近書かれたようにも読めるが、40年も前かぁ…。山への愛が伝わるエッセイで、行ってみたいと思うけど、今行ってみてももうすっかり変わってしまってわからないところが多いんだろうな。富士山観測所の設置や駐在時のお話がおもしろい。気象庁に勤めていたとは知っていたが計測機械担当だったとは。気象予報士のような予報の知識はあまりないというところに、なんとなく親近感。2021/05/08
roatsu
8
今から数十年前の登山の様子がうかがえるエッセイ集。新田次郎さんらしく仕事で関わりの深かった富士山や気象のこと、手つかずの自然に溢れていた頃の霧ヶ峰のことなどあれこれ面白い。本当にスローペースで汗が出ないように歩き、休憩は殆どとらないというスタイルは俺自身の山歩きに似ているので親近感が湧いたり(笑)。南アルプスへの山行記が特に印象深かったかも。今夏に霧ヶ峰をハイキングしたけど、素敵に思えたあの高原も彼が少年期を過ごした往時の自然はもうないのだなと少し悲しくなったり。2014/09/27