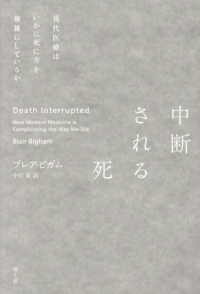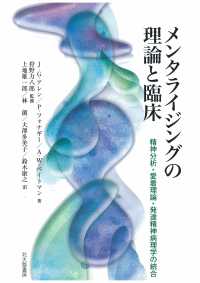内容説明
難しい専門用語も丁寧に解読しながら、古典的イスラーム法から近代国家におけるイスラーム法までを概説した唯一の書。
目次
第1章 『クルアーン』の立法
第2章 正統カリフ・ウマイヤ朝期の国家と法
第3章 古典法学の完成
第4章 古典期の法学と法学派
第5章 ファトワーはなぜ発行されるのか
第6章 慣習による法の変化
第7章 エジプトにおける民法典と身分法典の編纂
第8章 パキスタン刑法典
著者等紹介
堀井聡江[ホリイサトエ]
1968年生まれ。上智大学法学部国際関係学科卒業。ケルン大学哲学部東洋学科博士課程修了(Ph.D.)。現在、東京外国語大学、東北学院大学非常勤講師
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
牛タン
2
内容:ウマイヤ朝・アッバース朝におけるイスラーム法学の発展(特に正統四法学派の成立)、四法学派による「慣習」の取り扱い、エジプト民法典・パキスタン刑法典の編纂と適用。感想:思想と歴史、学説と判例が常にセットで紹介されており、理屈と実際の出来事の関係が掴みやすい。また、本書で新出の用語については解説があり、本書で同じ概念や学説が繰り返し出てくる場合には前出の参照が丁寧に記されており、しかも詳細な索引も用意されている。法学派間、法学派内での学説の類似点・相違点なども丁寧に解説されている。すごく良い本だと思う。2015/12/29
西夏
1
イスラーム法の歴史から現代における適用までを抑えた本。イスラームについて勉強している人でも、イスラーム法に詳しいという人は珍しいのではないだろか。法学派によって解釈が異なるのは意外であった。 イスラーム法が法学者や裁判官の様々な努力を経て現代にある程度適用されているのに対し、日本の憲法は輸入品な感じがすると初めて感じた。2014/12/25
抹茶ケーキ
0
イスラム法の歴史。四学派などの学説が整理されていて分かりやすかった。イスラーム法が慣習や政治状況に応じて比較的柔軟に変容してきたことがわかった。近年の運用についてはパキスタンの判例を事例にして論じられており、そこが一番面白かった。2016/04/10
kenken
0
流れが頭に入ってきて、いいタイミングで読んだ。2010/05/30
ヨシツネ
0
マザーリム法廷について書かれているのが嬉しい。ただ軍事法廷になる理由はカリフの権威の分担だからなのかが知りたかった2021/06/26