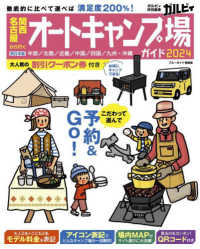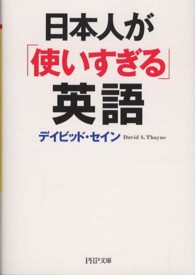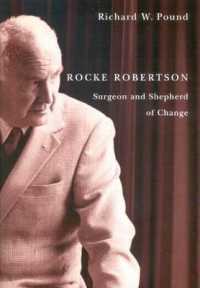出版社内容情報
著者が早稲田大学の教養科目としておこなう授業をもとに、家族史からグローバル・ヒストリーまでをあつかう入門書。
歴史における家族、女性性や男性性の変容、男女二元化のプロセス、身体的性差の認識の変化といったジェンダー・イシューに、
歴史学がどのような問題意識をもってアプローチし解き明かしてきたかを、紐解いていく。
内容説明
「女らしさ」/「男らしさ」、「女であること」/「男であること」の意味は普遍的でも不変的でもない。ジェンダー・イシューに対して歴史学はどのようにアプローチしてきたのか、西洋ジェンダー史の視点から考察する。ジェンダー秩序からの解放が求められている今だからこそ、手に取ってほしい一冊。
目次
第1章 「古き良き大家族」は幻想―家族史
第2章 女性の歴史が歴史学を変える―女性史
第3章 女らしさ・男らしさは歴史的変数―ジェンダー史
第4章 男女の身体はどう捉えられてきたか―身体史
第5章 男はみな強いのか―男性史
第6章 「兵士であること」は「男であること」なのか―「新しい軍事史」
第7章 西洋近代のジェンダーを脱構築する―グローバル・ヒストリー
著者等紹介
弓削尚子[ユゲナオコ]
お茶の水女子大学大学院人間文化研究科単位取得退学。博士(人文科学)。早稲田大学法学学術院教授。専門はドイツ史、ジェンダー史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Y2K☮
36
こんなシステムは不条理だと感じても「みんな従ってるし」と諦めることが誰しもある。だが本当に変え難いのか? 世界の流れを決めているのは概ね白人の年配の男性。人種の異なる若い女性は三重の意味で不遇を強いられているかもしれない。皇位の男系&男子縛りと同様、古き良き伝統と見做される家族観の歴史も実はさほど長くない。女性への蔑視は少数者や他民族、異文化へのそれを正当化することに容易に繋がる。男性も他人事じゃない。ステレオタイプな「男らしさ」の押し付けは戦争反対の声を潰す要因になり得る。当たり前、前提、常識を疑おう。2022/05/10
松本直哉
30
タイトルから想像される広く浅い入門書ではなく、トピックごとの掘り下げが深くて読みごたえがある。当たり前と思われている現代の性規範を、時間を超えてプレモダンと、空間を超えて非西欧世界と参照して相対化・異化してゆく。とりわけ男性史の視点から見た男の体液(涙を流すことの禁止と自慰の禁止の相関関係)、また近代になって軍隊が男性だけのものになるにつれて「産む性」に対する「殺す性」として男性が規定されてゆくこと。参考文献も充実していて読みたい本が一気に増える。図書館で買ってもらったが自分用に一冊手に入れてもいいかも。2022/06/19
buuupuuu
10
旧来の歴史学に対して、家族史や女性史は無視されてきた領域や排除されてきた存在を発掘して、私達の認識を新たにした。ジェンダー史は、性差についての私達の考え方がいかに時代とともに変化し、私達のあり方を規定してきたかを教える。人々をカテゴライズするものとしての性差が際立つようになったのには、身分制の崩壊や国民国家の成立が関係しているという。ジェンダー史が明らかにするのは、差別の様態を越えて、性差に関連してどのような秩序が成り立っていたかである。その点からすると、男もまたジェンダーに規定されてきたと言える。2022/02/12
カモメ
5
歴史の中で夫婦は共同で労働し生計を立てていたが近代家族モデルでは愛情に重きがおかれるようになる。しかしこれはあくまでモデルであり農民家族や工場労働者家族は総出で働き家計を支えたそうで、前近代の身分制社会においては男女の差異以上に身分の差が重くのしかかっていた。18世紀末以降は男女の身体的性差へ関心が高まり男女二元論が顕著となっていく。出産は近代医学の対象となったことで産婦と産婆からなる女性たちの問題に男性が介入し主導権を握ることを意味したというのは、近代化と男性の権力化の繋がりについて考えさせられる。 2022/07/03
てまり
2
ジェンダーの視点が旧来の歴史学にもたらしたもの。「人類の基本形=男性」というフィルターを外すと見えてくるもの。最終章、植民地支配への問い直しが大変にグロテスク。西洋人は道徳的かつ男性的なもの、非西洋は自堕落で女性的という枠組からの加害。本の前半に18世紀以前くらいは男女の身体は別個の確立したものでなく連続したものとして捉えられていたという話(平等という認識ではない点に注意)があるが、その時代が過ぎ、明確な区別とレッテル貼りが横行したためということもあるのかなと思った。2022/04/07
-
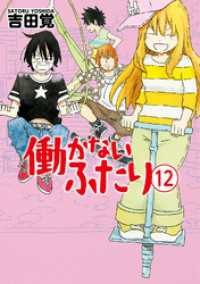
- 電子書籍
- 働かないふたり 12巻 バンチコミックス