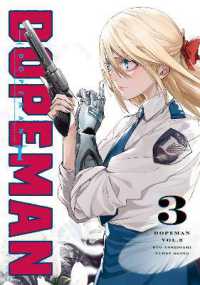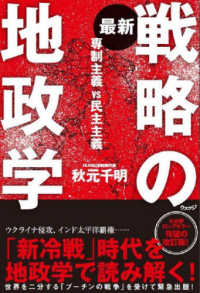出版社内容情報
戦国時代の合戦で〈大敗〉すると、どのような事態が生じるのだろうか。
〈大敗〉と滅亡、その因果関係は疑いもないように思えるが、滅亡に直結しないケースは多い。本書では〈大敗〉の影響を、実証的な歴史学研究の方法によって確かめていく。
内容説明
川中島の戦い、桶狭間の戦い、長篠の戦い…合戦での“大敗”は、大名の滅亡に直結するのか。逆境を乗り越え、“大敗”の教訓を活かす道は―“大敗”後に着目し、敗者のゆく末を考える。
目次
序 “大敗”への招待
第1部 “大敗”と大名領国(長篠の戦いにおける武田氏の「大敗」と「長篠おくれ」の精神史;木崎原の戦いに関する基礎的研究―日向伊東氏の“大敗”を考えていくために;耳川大敗と大友領国)
第2部 “大敗”と「旧勢力」(大内義隆の「雲州敗軍」とその影響;江口合戦―細川氏・室町幕府将軍の「大敗」とは;今川義元の西上と“大敗”―桶狭間の戦い)
第3部 “大敗”から勝者へ(“大敗”からみる川中島の戦い;三方ヶ原での“大敗”と徳川家臣団;伊達家の不祥事と“大敗”―人取橋の戦い)
著者等紹介
黒嶋敏[クロシマサトル]
1972年生。現在、東京大学史料編纂所画像史料解析センター准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
六点
11
戦国時代に少しでも関心があれば「武田氏の長篠」「日向伊東氏の木崎原」「大友氏の耳川」「大内氏の雲州攻め失敗」「細川氏の江口合戦」「今川氏の桶狭間」「伊達氏の人取橋」などを題材に中堅の研究者による共同研究の成果である。そもそも史料としての家譜の史料批判から始めなければならないもの、敗軍側に取って果たして痛手であったか否かを再検討を要するもの、一口に大敗と言っても、後世に与えた影響は様々である。敗軍の苦い記憶が、世代を経て顕彰の対象にすらなったりする。歴史研究の妙味と地味さと面白さの最前線から伝える本である。2019/07/14
MUNEKAZ
10
テーマが面白い論集。個人的には大友家にとっての耳川合戦、大内家にとっての月山富田城攻めなどあまり読む機会の少ない西国の「大敗」が面白かった。耳川合戦などは前線指揮官の大量戦死による世代交代の失敗、占領地で相次ぐ有力国人の謀反と桶狭間後の今川家に共通する部分も多いことに気付かされる。また徳川家にとっての三方ヶ原、伊達家にとっての人取橋など、最終的に勝者となった家の「大敗」の扱われ方も興味深かった。前者は武功を示す場として積極的に語られ、後者は「苦戦」と読み替えられて歪な伝承が残されている。2019/06/08
オルレアンの聖たぬき
2
大名家の『敗北』とは史実とは違うかもしれないと何度もうなづきながら読んだ。衝撃だったのが『今川家の桶狭間』衝撃的だった。動機が上洛だったか何だったか以前に桶狭間戦場以外の戦線がどうなっていたかを知っていればわかるはず。これは読んで良かった本。2021/10/08
katashin86
2
「大敗」はそもそも言われている通りに大敗だったのか、大敗が滅亡に直結したのか、生き残った大名家が大敗をどう位置付けたのか、さまざまな大敗とさまざなな論点の本。2020/04/14
wuhujiang
1
<大敗>の前後の政治史を明らかにする論文集。 ただ、内容は合戦そのものの研究よりかは ・先行研究 ・対象合戦の史料とその性格の検討 ・なぜ大敗に至る行動を起こしたのか ・大敗後はどう行動し立て直しを図ったのか がメインと感じる。 大敗という大事件は記憶に残り、軍記ものなので様々な創作が行われてしまう。その中で当時の史料をあたり、先入観をとりのぞいた実像を明らかにするのは大仕事だし、大いに意義があると感じた。
-

- 電子書籍
- 俺一人だけカンストレベル帰還者【タテヨ…
-
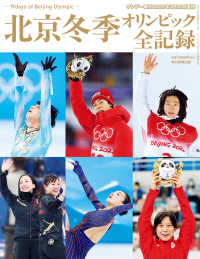
- 電子書籍
- サンデー毎日増刊 北京冬季五輪