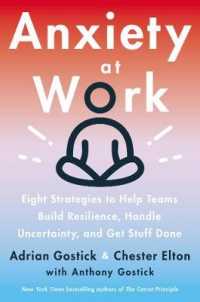内容説明
日本の民俗学は柳田国男によって開拓され、確立したことはまちがいない。しかし、すべてを柳田に始まり、柳田に終わると解釈してはならない。近世以来の文人たちによる民俗の発見があり、明治以降の欧米人類学の導入があった。明治末の柳田国男の登場で、それらが統合され、民俗学が成立した。しかし、柳田以降にも、自己の問題意識で独自の民俗学形成に果敢に挑戦した人たちがいる。「野」の学問としての民俗学は多くの個性的な先達を持っていることを理解していただきたい。
目次
1 野の学問、民俗学
2 菅江真澄
3 鳥居龍蔵
4 山中共古
5 柳田国男
6 折口信夫
7 宮本常一
8 瀬川清子
9 アカデミック民俗学への道と研究者群像
著者等紹介
福田アジオ[フクタアジオ]
1941年生まれ。東京教育大学大学院文学研究科日本史学専攻修士課程修了。専攻、民俗学・日本村落社会史。現在、神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ムーミン2号
5
山川出版社の「日本史リブレット」の一冊だけど、「日本史」の中に「民俗学」も収められている点、個人的には画期的! と思った。さらに著者が(一度目にすると忘れられない)福田アジオである点は、本格的! と思った。内容はタイトルどおりで、近世・明治初期から、柳田国男、折口信夫、宮本常一そして女性研究者の瀬川清子と紹介がなされている。民俗学研究といっても一様ではなく、また各人の研究態度もそれぞれ個性的であるのがよくわかる。山川出版社からはこんなリブレットが100冊以上あり、世界史版もあって、面白そうだ。2022/05/09
ekura
0
著者にとっての民俗学は江戸時代から始まり、1970年代が「現在」らしい。そこが不満。2009/10/07
こまさん
0
日本で発達した学問である民俗学が、アカデミックな学問として成立するまでに尽力した方々の業績をコンパクトにまとめている。学問に対する真摯な姿勢は学ぶべき事が多い。2017/02/28
つきもぐら
0
山川出版社の歴史は面白いですね。リブレットには毎度お世話になっております。本書は民俗学を代表する人々の系譜を参照することができます。文章を書くにあたっては言葉が要りますが、言葉は本質的に過去の属性です。よって文章を得るためには歴史を遡ることになります。民俗学は日本史に置いて主要な登攀路のひとつです。柳田国男が発見した「民俗」は「過去の話ではない」ものでした。近代合理主義の立場ではありえない物語を、人々は実際に起こったこととして語ります。日本語に命を吹き込む「説話」文体の途上に豊かな民俗の語彙がありました。2016/08/07
双海(ふたみ)
0
本書には菅江真澄、鳥居龍蔵、山中共古、柳田国男、折口信夫、宮本常一、瀬川清子が登場する。2013/07/29
-

- 電子書籍
- 代理出産サセラレ妻 13話「信之の使い…