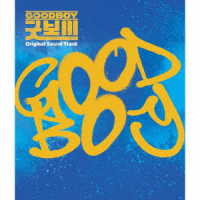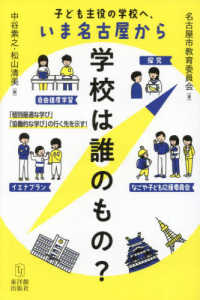内容説明
本書では、国人一揆をはじめとする武家の一揆、土一揆・荘家の一揆・宗教的一揆など、特色ある中世一揆の諸相を、まず具体的に跡づけてみる。そのうえで、とくに一揆契状や掟書など一揆の法に着目することで、一揆と権力の関係、さらには中世から近世への社会の移行の性格を、一揆という視点から考える。
目次
中世の一揆と近世の一揆
1 中世一揆の特色
2 中世一揆の流れ
3 中世一揆の要求
4 中世一揆の秩序
5 中世惣国一揆の法
6 中世一揆法の世界
一揆と権力
著者等紹介
久留島典子[クルシマノリコ]
1955年生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程中退。専攻、日本中世史。現在、東京大学史料編纂所教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Ikkoku-Kan Is Forever..!!
6
呉座勇一『一揆の原理』では、歴史学における議論では、一揆=人民闘争だと書いてあるので、その実態を確かめるべく、取りあえず、コンパクトの本著を読むと、呉座さんのいうことは嘘八百で、一揆研究はかなりの研究蓄積があることがわかる。その上で、気になるのは、“一揆の時代”というように、中世史において一揆というものがキーワードになるのはなぜか、という問題。その点については、直感的に、これは、「公共性」という議論が歴史学において如何に思考されてきたのかを確認し、その意味を検討する必要があるな、ということがわかる。2014/12/24
海星梨
4
一揆の中の法のはなしでして、むしろ一揆が法であるという内容なので、一揆が法に与えた影響というかもっと大きな社会全体の流れの記述を求めていたぶん、肩透かしを食らいました。一揆は同一という意味のものであり、同盟の約束事の中で使われ、仏教集団から生まれ、武士が使うようになり、戦国時代で段々階層が下のものが起こす行為に当てられていくようになったとのことで、一揆の語が明文化してある上層の人たちの間に使われていた時にどうであったかという内容らしい。一揆の語が約束事、集団、その行動と多義で区別する集中力が持たなかった。2019/02/26
陽香
3
201101202016/11/20
こずえ
2
一揆についてわかりやすく書いてある。大学入試の日本史でちょいちょい聞かれたりするテーマなので受験生が記述のネタとして知識を整理するのにも使える
中村蓮
1
一揆はその目的などさまざまであるが、一味同心という構成員の結束の強化を目的や構成員のみならず領域支配のための法としての性格を持つ一揆があったことが分かりました。多数決の原理や構成員の契約により法として機能するというあたり新しいと感じました。これほど近代的といってよい法の原理を持っていた国がなぜ、21世紀も四半世紀を経ようという年に選挙で家系図を持ち出す候補者を輩出するほど前近代的になったのか、謎は深まります。 2023/02/14
-
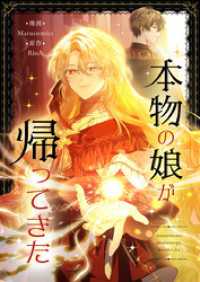
- 電子書籍
- 本物の娘が帰ってきた【タテヨミ】第2話…