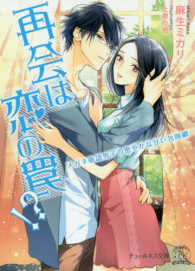内容説明
江戸時代は、キリスト教が禁止されていた時代だった。では、キリシタン(キリスト教徒)はどのように取り締まられたのだろうか。やがてキリシタンでないことを寺院が証明することになり、寺請・檀家制度が成立する。つまり、寺院は支配の末端機構となった。しかし寺院は地域において、様々な役割を果たすようになる。本書では、各地におけるキリシタン禁制の進展と、寺院の動向や民衆の宗教生活について見ていく。
目次
1 キリシタン弾圧の展開
2 キリシタン禁制制度の確立
3 宗門改はどのように行なわれたのか
4 地域における宗教生活
5 宗教施設の役割
6 キリシタン禁制の終末
著者等紹介
村井早苗[ムライサナエ]
1946年生まれ。日本女子大学文学部卒業。立教大学大学院文学研究科日本史専攻単位取得。専攻、日本近世史。現在、日本女子大学文学部助教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。