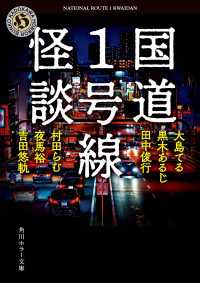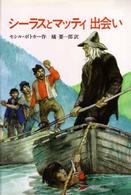目次
1 名所の橋(橋と柱;おうげの橋 ほか)
2 “粗末”な橋(いろいろな橋;m×n枚の橋 ほか)
3 橋と中世のみち(二枚橋;八ツ橋)
4 都市鎌倉とその周辺―中世的都市(水辺の空間;奥州へ ほか)
5 交通と都市的な場(荒井猫田遺跡;野路岡田遺跡;下古館遺跡)
著者等紹介
藤原良章[フジワラヨシアキ]
1954年生まれ。東京大学大学院人文科学研究科修士課程。専攻、日本中世史。青山学院大学文学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mk
4
絵巻物のなかの「橋」、都市鎌倉の幹線道路(「大手」)、そして考古学の発掘成果に見る街道沿いの町の三点が主題。中世人の「思惟」を主題にした論文集もある著者が、中世の多様な「みち」(海、陸、河川)をめぐって自由に展開する思考の通路を辿るのはなかなか楽しい。「東光寺」や「八ツ橋」のように、現代人の感覚では固有名詞に思える地名の古層をはぎとって、交通路との接点を論じる玄人好みの考証は、限られた字数ながらも光っている。著者の生活空間から出発して、中世に迫ろうとする足取りが想像できるようで、姿勢を正される思いがする。2018/08/08
イツシノコヲリ
3
都市というより道としての橋を中心に扱っている。街道の主流の橋がn枚橋だと考えられることが勉強になった。2023/07/09
考えない人
3
中世のみちはさまざまな人びとが行き交う場所であり、きわめて身近な存在であった。人がいればみちは必ずとおっているし、人が住み着いていないようなところにさえ、みちは確実にとおっていた可能性もある。みちをさがしていくことから、中世の人びとの暮らしを復元していく。過去と現在もまた、歴史というみちで繋がっているのだと思った。2023/04/08
たらら
3
道と橋はあったが都市は……。都市の入口と出口としての道ということはあるにはあったか。こういう中世の歴史を隙間を埋めるような良書はいい。当時の人と後世の人の意識が那辺にあったかを思うのは楽しい。2010/09/08
灰猫
2
道や橋の話がほとんどで都市は僅か。道に関してはせっかく陸上以外の交通ルートを道として考えるなら海路を考慮に入れて欲しかったなー。事例がかなり具体的なのでわかりやすいんだが、これを一般化していいかもまだまだ課題アリ。橋の宗教性については境界論からいうと納得できるけどその先行研究としてあげられてる折口信夫の研究が参考文献にないのですが!?2012/02/02