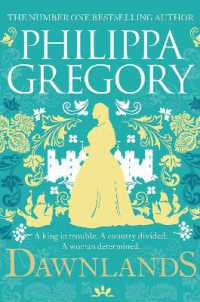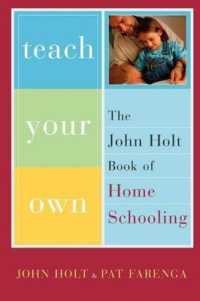内容説明
イタリアのムッソリーニは、第一次世界大戦直後、世界で最初にファシズム運動を創設し、3年後には政権を掌握、さらにその3年後から、全体主義的な独裁制に転換した。それらにはいかなる必然性と偶然性が作用したのか。革命派の社会党員からファシストに転じた彼は、何をめざしたのか。ヒトラーに崇拝され、ヒトラーと対抗・競争しながら、最後にはその従属的同盟者になったムッソリーニの行動と思想、その生涯に焦点を当て、イタリア・ファシズムを描き出す。
目次
三つのファシズムの終わり方
1 鍛冶屋の息子から社会党機関紙の編集長へ
2 第一次世界大戦からローマ進軍まで
3 ムッソリーニ政権の成立から独裁へ
4 「帝国」の建設と戦争
5 ファシズム体制の崩壊とレジスタンス
著者等紹介
高橋進[タカハシススム]
1949年生まれ。大阪市立大学法学研究科後期博士課程中退。専攻、ヨーロッパ政治史・イタリア政治史。現在、龍谷大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
MUNEKAZ
12
ムッソリーニのコンパクトな評伝。典型的なポピュリストというか、大戦の戦勝国でありながら勝利の分け前を得られなかったイタリア国民の鬱屈を利用して、国家の指導者まで登り詰めた印象。社会主義の闘士から国家主義者への転身も、時代の空気を敏感に読んだ結果であろう。ただ行動の人であって、理想はあれど計画はなく、世界大戦の大渦の中で主導権を失い、ヒトラーの後塵を拝すようになるのも宜なるかな。側近の裏切り、ドイツの傀儡、そして国民による断罪という流れは、最後まで自らの意志と狂気を通したヒトラーと好対照に思える。2020/11/24
ほうすう
10
ムッソリーニの簡易な評伝でありながら戦間期のイタリア情勢についても描かれている。読んでいて感じたのはずいぶん暴力に訴えて物事を進めている。政権を獲得するまでの過程でそんな暴力重視で行けるのかとちょっと戸惑うほど。ヒトラーに比べると冷徹さに欠けるし第二次大戦についても引きずられてしまっていた印象。このあたりが計画性の無さと言われてしまうのか。2021/06/20
相米信者
7
言わずと知れたイタリアの独裁者の評伝。熱心な社会主義者の父と熱心なカトリック教徒の母の間で生まれたムッソリーニは、思想面は父に影響を受け、母を後のファシズムの理想の女性像とした点が面白い。小学校の臨時教員、ボヘミアン的生活を通して社会主義運動に邁進したムッソリーニがやがて首相となり、ファシズム体制を築き上げた経緯は見所である。当初ヒトラーを軽蔑するも、やがてドイツに国力の差を見せつけられ、従属的になってしまう姿は滑稽と言った方がいいのか。右派ポピュリズムが台頭する現代欧州を知るためにも必読の書と言える。2020/05/26
ア
6
「不完全な全体主義」の主導者。若い頃には社会主義サークルに属していたことや、(ヒトラーと異なり)政権を支える理論やマスタープランの不在が興味深い。ファシズムや全体主義とは(そしてそれに対抗する共産圏の民主主義や西欧の自由民主主義とは)結局何なのだろう。2021/01/04
竜王五代の人
5
国威の発揚と領土の拡大を目標とし(これが副題の「帝国を夢みた」か?)、友人が持てず他人を信用できないので、結果として兼任が多くなる、女好きでもある(金銭欲は?)、表紙とかを見るに写真写りもなかなかよい、独裁者らしい独裁者、と纏められていたけどそういう読解でいいのだろうか? 大戦での主体性を失い、ドウーチェ解任あたりからもう脱け殻になっていた、というのも分かりやすいといえば分かりやすい。2025/08/11