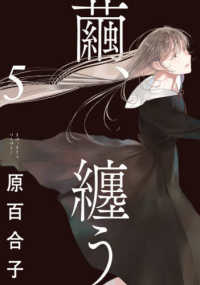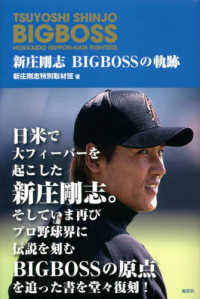内容説明
インドといえばわれわれが思い浮かべるイメージは、限定され、固定化している。「神秘の国」「悠久の国」といった憧憬を込めたイメージ、その一方で「カースト制度」「宗教対立」という後進的なイメージなど。こうしたイメージの固定は、どのように生まれ、そして、どのようにして突き崩されるべきなのか。イギリスによるインド支配期の諸側面を考察する。
目次
インド現代史をみる眼
1 イギリスのインド認識
2 近代インドにおける女性問題
3 インド民族運動と「コミュナリズム」
4 反カースト制度の潮流
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
組織液
17
イギリス史は好きですが、イギリス植民地時代のインドについてはあまり知らなかったので流し読み。カースト制度やヒンドゥーとムスリムの対立などは、イギリスが支配を存続させるために行った「分割統治」の結果という話は有名ですが、インド側が西洋に対抗して自己のアイデンティティを形成したという面もあるみたいですね。2021/02/19
ジャケット君
1
イギリスはインドの文明を『野蛮』とみなす理論を構築した。支配を正当化するための準備である。しかしながら、ヒンドゥー慣習は不可触民にも女性にも差別した準拠があり理性に従えば野蛮とみなされるのはやむなしだ。ジェンダーにおいては、ヒンドゥー教は日本の伝統慣習よりもひどい家父長制であった。サティーを代表とする。イギリスがインドに教育機関を設けていくうちに政治的にも女性の社会進出が都合がよく女性学校を設けた。社会変動の中でガンジーは寡婦となる女性を尊敬し女性が進出することをガンジーのイデオロギーではよいものだった。2024/10/02
sovereigncountr
1
イギリス植民地期のインドにおける様々な社会集団の動きを必要十分にまとめた名著。刊行は古いが、ジェンダーなどにも十分に目配りがされている。2023/09/09
よし屋
1
イギリス支配とインドの人々の相互のリアクションが結果としてカーストへの帰属意識を高めていく流れや、インド史の基本的なコンセプトがイギリス人の発明であるなど、一般的なインド観をひっくり返してくれるオドロキがありました。2015/10/10
tsuitsui
0
「伝統」と私たちが思い込んでいるものは実は「近代化」で自分たちで新たに作りだしたものだと思いました。 この話の場合インドでは「サティー」「幼児婚」をヒンドゥーの男性たちが西洋に文化的に対抗するために利用しました。弱いものがより弱い者負担を押し付ける。夫、父の言うことを聞く女性は彼らにとっては社会の美徳かもしれませんが、結局今日では低賃金で働かせたり、貧困の温床になっているように思います。 社会問題は他国を責めるのではなく、歴史を冷静に見つめ自国の制度を変えなければならないのかなと思いました。2013/08/08
-
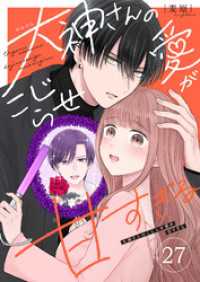
- 電子書籍
- 大神さんのこじらせ愛が甘すぎる【単話版…
-
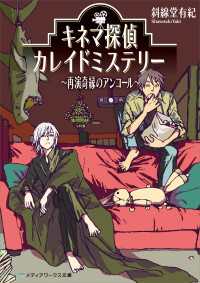
- 電子書籍
- キネマ探偵カレイドミステリー ~再演奇…