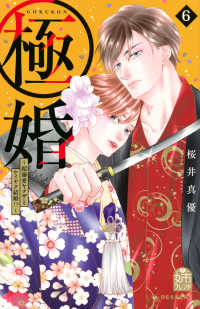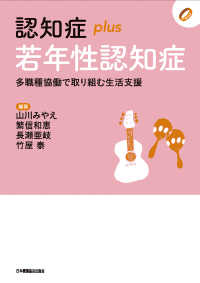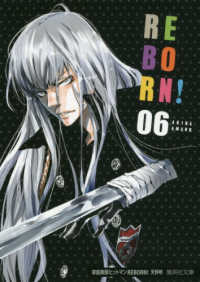内容説明
本書では、十九世紀初頭に独立をとげたラテンアメリカ諸国の発展を他地域との比較において論じ、さらにアメリカ合衆国との関係について簡潔な通史的叙述を提供する。
目次
1 ラテンアメリカ諸国の独立
2 輸出主導の経済成長
3 対米関係
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けーすけ
5
ラテンアメリカとは旧スペイン・ポルトガル領を意味し、旧英仏蘭植民地はカリブ地域と表される。この違いは宗主国の違いに基づく言語文化の違いや植民地開発開始時期の相違、独立や自治権獲得の違いへ帰着する。アメリカのモンロー主義はパクスブリタニカの下奏功したに過ぎないが、イギリスが軍事的にも経済的にも優位でありえなくなった19世紀末にアメリカがカリブ海政策を展開し、続いてプラット修正条項、棍棒外交、ローズベルトコロラリー、善隣外交、米州機構設立、そして低姿勢外交と手を替え品を替えラテンアメリカにアメリカは干渉した。2015/01/20
kanaoka 58
4
南米旅行の予備知識のため手に取りました。他のアフリカ・アジアの植民地との性格の違い、現在の民族構成・支配構造・経済構造、独立の経緯、米国との関係性の変遷など、理解することができました。2024/06/13
けーすけ
4
ラテンアメリカの独立から現代にいたる200年足らずの時期について綴られた本。「1904年12月の年次教書でローズベルトは『モンロー・ドクトリンから導かれるローズベルトの系論』として知られる新しい政策方針を発表した。…モンロー主義に立脚して…ヨーロッパ諸国の干渉を排除するについては…不当行為の被害を受けたヨーロッパ諸国は、アメリカをこれら諸国を庇護する従犯者とみなし、モンロー主義を不当とするだろう。アメリカ自身がラテンアメリカ諸国に武力介入し…いわば国際警察力として行動する必要がある」2014/12/15
らっそ
3
カストロ逝去からラテンアメリカに関心が出てきた。概略。クリオーリョの存在がラテンアメリカの特徴ってことでいいんだろうか2016/12/22
ぱに
2
なんせ予備知識が全くないため、内容全部その通りだと思って読むしかありませんでした。カリブに行くから読んでみようと手に取った本で、最初の方でラテンアメリカとカリブの違いが分かり、この本カリブについての本じゃないじゃん!ってなったけど、勢いで読みました。98年初版の07年6刷なので、それなりに需要があるんだろうと思いつつ、世紀が変わっても、新しい情報が加筆されない辺り、そこまで需要がないのかも、とも思う。クリオーリョとクレオールの違いも、この前疑問に思ったところだったけど、この本に書いてあることで納得した。2016/11/03