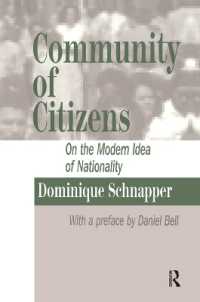出版社内容情報
これまでは「軍事施設」中心で語られてきた城郭研究において、近年、研究の進展により、そもそも「城とは何か」という点が注目を集めています。
そこでキーワードとなるのが「祈りの場」「権威の源」としての城の姿です。本書は、充実の一途をたどる城郭研究の新たな潮流に注目し、城郭史を「陰陽道」「鎮守」「呪い」「祈り(宗教施設)」という観点から捉えなおすことを目的としています。
具体的には、石垣に使われる転用石について、従来は石材不足を補うといった実用面、または戦国武将が不信心であることの証左として語られることが多かったのに対し、本書では、転用石を逆さに積むことで「けがれの逆転」を意図しているのではないかとの仮説を立てています。
このように、築城に当たっての場所選びから普請・作事にいたるまで、中世の呪術的な意識と儀礼がどのように作用していたのかを読み解きたいと考えます。
内容説明
立地、縄張、建造物、儀式にいたるまで、全国各地の城郭に見え隠れする、「信仰の場」としての姿。「軍事拠点」だけでは語れない、城郭の存在意義を見直す!
目次
序章 戦国時代における呪いと祈り
第1章 聖地としての城―地選・地取における呪術の役割
第2章 神様の名が残る城―縄張からみた信仰の足跡
第3章 転用石・鏡石・猪目石の役割を見直す
第4章 天守・櫓に込められた呪いと祈り
第5章 「人柱」はあったのか―地鎮の作法
第6章 城における鎮守と結界のかたち
終章 近世の城と城下町への継承
著者等紹介
小和田哲男[オワダテツオ]
1944年静岡市生まれ。早稲田大学大学院文学研究科博士課程修了。文学博士。静岡大学名誉教授。日本城郭協会理事長。専攻は日本中世史、とくに戦国史。また、「秀吉」「功名が辻」「天地人」「軍師官兵衛」「麒麟がくる」など、NHK大河ドラマの時代考証をつとめる。現在、YouTubeで「戦国・小和田チャンネル」を配信中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
榊原 香織
乱読家 護る会支持!
とりもり
takao