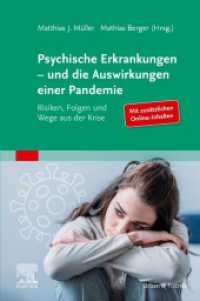内容説明
スポーツ人類学、スポーツ教育学、スポーツ政策学の各方面からeスポーツの様々な可能性を探る。
目次
第1章 eスポーツの概要と現状(eスポーツの概要;eスポーツ業界の現状 ほか)
第2章 コンピューターゲームによる競技はスポーツなのか?(コンピューターゲームの歴史;競技会の開催とプロゲーマーの出現 ほか)
第3章 eスポーツに教育的効果はあるか?(教科体育の教育的効果とeスポーツの関係;体育科・保健体育科の実情とeスポーツの教育的効果 ほか)
第4章 eスポーツの普及のために必要な施策とは(「ヒト」は誰が管理するのか;「モノ」の視点からeスポーツを考える ほか)
著者等紹介
田簑健太郎[タミノケンタロウ]
日本体育大学大学院体育学研究科(修士課程)修了。専攻、スポーツ史・スポーツ人類学。現在、流通経済大学スポーツ健康科学部大学院スポーツ健康科学研究科教授。東京体育学会常任理事。龍ケ崎市スポーツ推進計画審議会会長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Tenouji
18
年甲斐もなくスプラトゥーンを始めて、自称4歳のプレイヤーにボコられる毎日w。YouTubeには、如何に勝つかの解説動画がアップされていて、上手いプレイヤーはバトルに必要な概念を的確に説明してくれている。オンラインバトル相手のマッチングは自動で行われ、ある意味、短時間のバーチャルサバイバルゲームでもあり、チーム内の役割分担を即座に判断し行動に移す必要あり。スキル評価は明確な基準で、これも自動で行われ、自らの成長がわかる仕組みや、振り返りのためのデータもある。おそらくこういうことをeスポーツというw。2021/09/12
スプリント
8
可能性は満ち溢れているが危うさも感じるeスポーツ。 成熟するには業界内部の成長と統制も必要と感じた。2022/05/29
電気石
2
eスポーツは、知れば知る程魅力的だよなと思う。自分が幼い頃からゲームに触れて楽しむことが出来たのは、ゲームをしていた父親のおかげだ。テレビでeスポーツや選手について取り上げられることもあり、身近な存在になっているのではないだろうか。親からゲーム類を禁止されていた友人が身近にいたからこそ、社会でのゲームの存在が昔と比べ変化していることを実感する。性別や身体的格差が問題になりづらいとあったが、現状は偏っていると言わざるを得ない。これから先、この世界はまだまだ発展していくだろうから、注目していきたい。2021/10/24
-

- 電子書籍
- 日本の大問題が面白いほど解ける本 - …