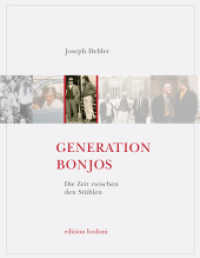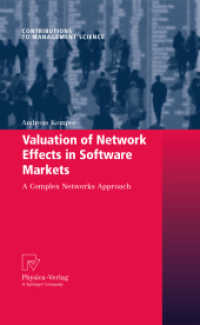内容説明
飢饉、大地震、京中の大火、「世の不思議」をたびたび体験し、書き記した長明は、五十の春を迎えて家を出る。時代の波に翻弄されつつも、身をもって時代に立ち向かった長明の精神性を、『方丈記』『無名抄』などの著作から読み解く。
目次
1 若き日々(行く川の流れ―鴨氏人の世界;糸竹・花月を友とせん―若き頃 ほか)
2 和歌の道(一つの庵をむすぶ―新たな出発;いみじき面目―『千載集』 ほか)
3 奉公の勤め(歌の事により北面に参り―正治・建仁の頃;御所に朝夕候し―和歌所の寄人として ほか)
4 庵から問う(出家を遂げて―日野山の奥に;閑居の気味―方丈の庵にて ほか)
著者等紹介
五味文彦[ゴミフミヒコ]
1946年生まれ。東京大学文学部教授を経て、放送大学教授。東京大学名誉教授。『中世のことばと絵』(中公新書)でサントリー学芸賞を、『書物の中世史』(みすず書房)で角川源義賞を受賞するなど、常に日本中世史研究をリードしてきた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かわかみ
4
「方丈記」、「無名抄」(歌論書)、「法心集」(仏教説話集)を遺した鴨長明の評伝。源平合戦の動乱期の優れた文人であった長明が朝廷において歌人として成長していった道筋を詳しく説明している。残念ながら、最も関心があった出家後の長明の生き方に割いた紙幅は少ない。ただ、長明は出家してすぐに方丈の庵を結んだのではないこと、仏道に励むために出家した後のことを詳しく方丈記に記さなかったことがわかった。神官としての出世が果たせず世を拗ねて出家したようにも言われる長明だが、その心根は真面目だったようである。2022/05/07
um
0
詩人として読み解くのはあまりおもしろくない。たしかに言葉は残されているから、そこから読み解けるものはたくさんあるけれど、楽器を弾いたり念仏を唱えたり、あるいは歌を詠むときの息づかいみたいなものが気になる。2025/06/06