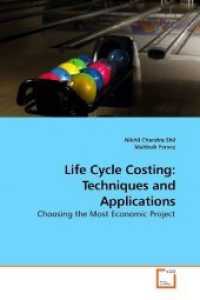内容説明
文字記録以前から、我が国は大陸と交渉をもっている。その中の最大の出来事は「漢字」の伝来である。文字の獲得とともに遣隋使・遣唐使の二十数回の派遣は、我が国の中国文化の影響を決定的にした。以後、教養の第一は漢文学である。知識人は漢詩もよく作った。本書は日本漢詩の流れを、第一期奈良・平安時代、第二期鎌倉・室町時代、第三期江戸時代、第四期明治維新以降としてとらえる。
目次
侍宴(大友皇子)
銜命使本国(阿倍仲麻呂)
秋日別友(巨勢識人)
後夜聞仏法僧鳥(釈空海)
不出門(菅原道真)
秋宿駅館(橘直幹)
山居(釈道元)
示虜(釈祖元)
題可休亭(釈円旨)
題壁(釈寂室)〔ほか〕
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
星規夫
0
漢詩も有名どころを一通り読まねば、などと低い志をもって図書館に行った時に発見したのがこの本だった。日本人が作る漢詩はどんなもんなのだろう、と思って読んでみたが、やっぱり中国ちっくな風景が目に浮かんできて、なんだかしっくり来なかった。と思いきや、20世紀の漢詩である『党人歎』(安井朴堂)や『原爆行』(土屋竹雨)などはとても新鮮で興味深く思われた。特に後者は、原爆投下直後の惨状とそれに対する嘆きが鮮烈に表現されている。2014/12/04
きさらぎ
0
継続してパラパラめくってるけど、あんまりこれ通読する本じゃないのでひとまず読了登録しとく。150以上の詩が載っていて、分量的に多いのは多分江戸時代の儒学者・幕末の志士。あと明治が少し。撰詩が良いのか解説が巧みなのか、初心者にも気持ちよく楽しめます。図書館で借りてきたけど、古書で送料込み500円とかだったので、手許に置いて折々パラパラしようと思います。そういう本。2014/08/23
うな坊
0
よんだずら。2014/04/02