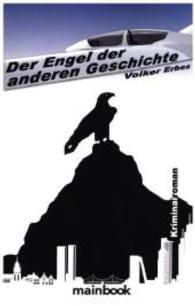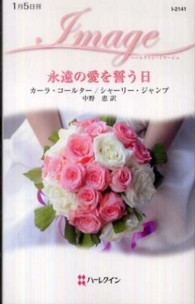出版社内容情報
「それにしても、震災前と震災後では、ぼくの書き方はガラリと変わってしまった」。
「幸福な水夫」(2010年発表)、「突風」(2015年発表)の小説2篇と書き下ろしエッセイ「黒丸の眠り、祖父の手紙」を収録。書き方は変わっても、郷里の家族とちいさな命を見つめるまなざしは変わらない。温かな、ときに激しい南部弁の響きに満ちた作品集。
著者略歴
木村友祐(きむらゆうすけ)
1970年生まれ、青森県八戸市出身。八戸を舞台にした『海猫ツリーハウス』(集英社、2010年)でデビュー。ほかの著書に『聖地Cs』(新潮社、2014年)、『イサの氾濫』(未來社、2016年)、『野良ビトたちの燃え上がる肖像』(新潮社、2016年)がある。2013年、フェスティバル/トーキョー13で初演された演劇プロジェクト「東京ヘテロトピア」(Port Bの高山明氏構成・演出)に参加、東京のアジア系住民の物語を執筆(現在もアプリとなって継続中)。詩人・比較文学者の管啓次郎氏の呼びかけで2014年よりはじまった「鉄犬ヘテロトピア文学賞」の選考委員もつとめる。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ruki5894
18
自分の家族と重なって何度も泣いてしまった。家族は重い、しんどい。愛されて手を掛けて育ててもらったとわかっているから。だから苦しい。車椅子の父親と2人の息子の温泉旅。このガサガサした感じがリアルたわ。他の2篇も通して中央と地方、戦後から未来へと同じテーマが横たわっている。なんといっても、この方の題名のセンスがとても好き。良い小説だった。また好きな作家が増えてしまった。2020/01/05
a43
8
まず。凝った装丁だと思った。あと、昨日から、著者初読みで4冊目にして。あぁ、この方は自分のアイデンティティを切り売りするのに長けておられるのか。この本はエッセイ付きでした。南部弁難しい。まぁ津軽弁もちゃんと言えないけれど。(しかし、八戸市出身の作家がアツイ。「八戸ブックセンター」のカンヅメからよい作家さんが生まれるといいね)←ローカルトークで対不起2020/01/26
今庄和恵@マチカドホケン室コネクトロン
7
件の騒ぎまでこの作家さん恥ずかしながら知らず。装丁の美しさに驚き。これは大切にされてる作家さんなのだなあ。ちょっと例えが変かもですが、「阪急電車」に関西弁が使われていないのが違和感で内容にのめり込めなかった。方言の多用は舗装されていない道を歩くようなものでスムーズに読み進められないこともあるけど、土地の空気を肌で感じることができる。その土地という設定が必然であるならなおさらのこと。巻末の書き下ろしも含めどの掌編にも戦争が影を落とす。今こそ読むべし。このデリケートさは古市センセは真似できんだろ。2019/08/29
UNI/るるるるん
4
南部弁が、予想外に頭に入る。年老いた父と、兄弟の三人旅。生まれたての仔猫と、要介護の父との対比が残酷なほどくっきりと表される。もっと心をえぐられてみたい。そう思える作家さんだった。八戸ブックセンターの企画として刊行されたこの本、三種類の紙が使われていてそれが楽しい。2019/09/06
mick
4
東北弁は馴染みが薄く、黙読だとピンと来ないのだが、声に出してみると不思議と意味が伝わってくる。装丁が美しく、凝っているのが印象的。内容から戦争へのメッセージを強く感じる。あーその通り。2018/05/14