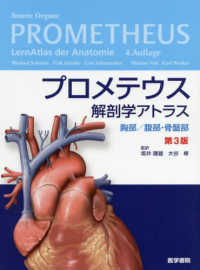出版社内容情報
地域の未来は、地球の未来は、はたして持続可能か。気候危機をはじめとする喫緊のさまざまな環境問題が人類全体に重く問いかけている。社会運動は市民社会の〈声〉であり、社会問題のすぐれた社会的表現であるとともに、社会変革の原動力でもある。本書は、環境研究や社会運動研究の国内外の理論的・実践的蓄積を踏まえ、そこに潜勢力をもった創造的な営為を見出し、意味づけをはかる社会学的な〈まなざし〉を提示する。
内容説明
環境社会学からみる地域と地球の持続可能性。環境からの問いかけと、応答する社会運動。試行を続ける市民社会の過去から未来へ。
目次
第1章 環境社会学と社会運動―市民社会の“声”と“まなざし”(環境社会学の成立と社会運動;日本の環境社会学の成立と特質 ほか)
第2章 環境社会学のグローバルな分析視角と環境正義運動―環境破壊のロジックと社会的公正に向けた制度生成の展望(環境問題はいかにして社会学の説明要因になりうるか;環境社会学の誕生と「加害‐被害構造」論、「新エコロジカル・パラダイム」論 ほか)
第3章 国土と資源を問い直す運動が“内破”するもの―戦後日本の開発と山水郷Bio‐region(国土開発と資源動員―日本近代史を開発社会学としてひもとく;開発に抵抗して内破に至る―昭和後期日本の運動経験 ほか)
第4章 ボトムアップの社会づくりを支える力―世界の二項対立を超える「市民」のあり方を求めて(激動する世界と「市民」への期待;市民と市民社会の「非西洋的」理解 ほか)
第5章 市民的不服従の社会学理論―自己・文化・コミュニケーションの側面からの規範的正当化(「環境と運動」と市民的不服従;市民的不服従の政治学理論 ほか)
著者等紹介
長谷川公一[ハセガワコウイチ]
1954年生まれ。現在、東北大学名誉教授、尚絅学院大学特任教授。国際社会学会クリスタル・アワード受賞(2014年)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。