出版社内容情報
平安時代中期にその後の仏像の祖型を完成させた定朝、鎌倉時代に最高峰を極めた運慶と快慶。今なお模範であり続けるこの仏像群は、現在の仏師の目から見てどう映るのか。仏師として長い経歴を持つ著者が、インドにおける仏像の濫觴から日本の慶派に至るまでの流れを通観しつつ、独自の視点で新たな日本仏像史を描き出す。
内容説明
平安時代中期にその後の仏像の祖型を完成させた定朝、鎌倉時代に最高峰を極めた運慶と快慶。今なお模範であり続けるこの仏像群は、現在の仏師の目から見てどう映るのか。仏師として長い経歴を持つ著者が、インドにおける仏像の濫觴から日本の慶派に至るまでの流れを通観しつつ、独自の視点で新たな日本仏像史を描き出す。
目次
序 一刀三礼、仏のかたち
第1章 日本の仏教黎明期―飛鳥・白鳳期
第2章 国家仏教として―奈良期
第3章 仏教文化の絢爛―平安期
第4章 藤原氏の栄華―摂関期
第5章 作善の仏像―院政期
第6章 慶派の興隆―鎌倉期
終 仏師の冬、そして現代へ
著者等紹介
江里康慧[エリコウケイ]
仏師。1943年生まれ。1962年京都市立日吉ヶ丘高等学校美術課程彫刻科卒業。仏師松久朋琳師・宗琳師に入門。独立後、父・宗平とともに仏像制作に専念。2003年京都府文化功労賞受賞。2007年財団法人仏教伝道協会より仏教伝道文化賞受賞。龍谷大学客員教授、同志社女子大学嘱託講師等を歴任する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ネギっ子gen
oldman獺祭魚翁
Tenouji
takao
Go Extreme
-

- 電子書籍
- すべてはお嬢様の手の中に【タテヨミ】第…
-
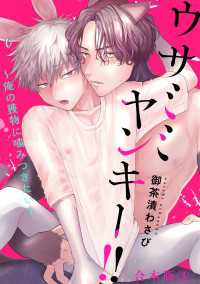
- 電子書籍
- ウサミミヤンキー!! 合本版3~俺の獲…
-
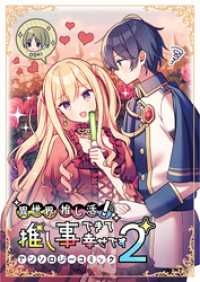
- 電子書籍
- 異世界推し活! 推し事できて幸せですア…
-
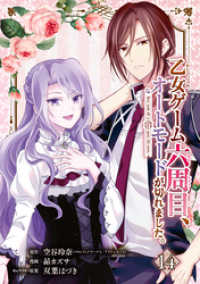
- 電子書籍
- 乙女ゲーム六周目、オートモードが切れま…
-
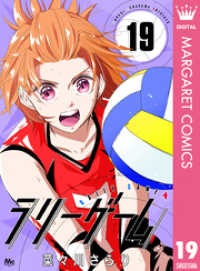
- 電子書籍
- ラリーゲーム 19 マーガレットコミッ…




