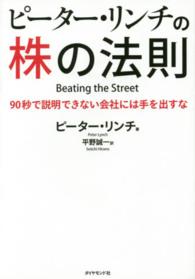出版社内容情報
小学校高学年(四?六年生)は、身体の成長とともに、こころも変化する時期である。「発達検査」では、思春期入り口のこころと身体は測れない。子どもの身体のSOSの奥に潜む心理的要因と発達障害の特性を考え合わせ、精神科医だからできる介入方法を語る。高学年ということを念頭に置き、子どもの未来を考える一冊。
内容説明
「発達検査」で測れない思春期の隠されたこころ。精神科医が診るこころと身体。
目次
序章 小学校高学年に学ぶ
第1章 発達検査って何?―支援や診断への大きなヒントを見る(発達検査、しています;数値以外の情報;心理検査は導きの糸 ほか)
第2章 起立性調節障害の落とし穴―隠れている自閉スペクトラム症(治療の焦点;起立性調節障害;身体表現性自律神経機能不全 ほか)
第3章 症例集―小学校高学年が映す世界(小学校四年生;小学校五年生;小学校六年生)
終章 「子どもたち」のために出来ること
資料 遠い風景―事件となった事例
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
shiiiiiino
0
症例がとても多く、数年にわたっての薬の対応や両親や子との問診まで、細かく書かれている。男子の発達が多めかという印象。シリーズものらしいので他の著書も読みたい 2024/04/04
めご
0
症例がわかりやすかったです。でも、この程度でも発達障害と診断されるのか、と感じてしまいました。2023/06/28
ᚹγअәc0̸א
0
・このシリーズが症例紹介が豊富なので有難い。本書ではWISCの説明に重点が置かれている。VIQ-PIQ discrepancyが少ない症例も複数紹介頂き、安易なWISC重点主義に釘を刺している姿勢が嬉しい処。 ・著者はもともと精神病理学畑のせいか、豆知識の豊富さも嬉しい。K-ABCの根底の1つにはルリアの神経心理学があるのですね。
-

- 和書
- スペインの歴史的現実
-
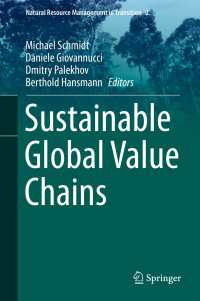
- 洋書電子書籍
- 持続可能なグローバル・バリューチェーン…