出版社内容情報
柳田国男(1875年から1962年)民俗学者。
近代において個人の記憶や体験が科学とみなされることはほとんどなかった。その中にあって柳田国男は自身の、そして無数の生活者の記憶や経験を堆積させることによって、その背後からひとつの歴史を描き出した。青年詩人、農政学者、官僚から民間学者へと転身し、日本の民俗学の礎を築き上げた知の巨人の全貌を描く。
内容説明
無数の生活者の詩を集め、そこに歴史を見出し、民俗学を創始する。
目次
序 体験を記述するということ
第1章 はじまりの風景
第2章 青年詩人
第3章 官僚時代
第4章 模索の時代
第5章 民俗学の確立に向けて
第6章 戦時下における体制化
第7章 保守主義者としての戦後
第8章 総合される記憶
著者等紹介
鶴見太郎[ツルミタロウ]
1965年生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程修了、博士(文学)。現在、早稲田大学文学学術院教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
owlsoul
9
日本民俗学の礎を築いた柳田国男。日本全土を旅しながら各地に残る民話や風習に触れ、その重要性に気づいた彼は、それらを調査・蒐集することに人生を費やした。政治が国家と個人の問題として語られる近代において、柳田はそこに「群(むれ)」という概念を持ち込み、共同体に根付いた文化の価値を訴えた。たとえそれが妖怪や祟りなど客観的には不合理に見えるものであっても、語り継がれる「群」の中で共通認識として機能していれば、それは政治的意味を持つ。学問と文学、そして政治の境界を跨ぐ柳田の仕事は、民俗という概念の奥深さを伝えている2025/05/11
志村真幸
2
「ミネルヴァ日本評伝選」の一冊。 柳田の生涯と仕事がバランスよく説明された一冊だ。読みやすく、親しみやすい文体で、また柳田への過剰な敬慕のようなものもなく、信頼できる一冊と思う。 従来からの評価と、著者ならではの新しい視点とが調和的に混ぜ合わされている点もいい。 柳田について詳しく正確に知りたいと思ったら、まず手に取るべき一冊だろう。 2024/07/10
-
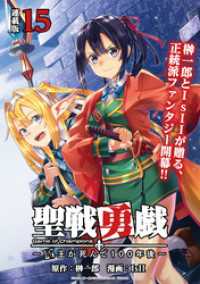
- 電子書籍
- 聖戦勇戯~魔王が死んで100年後~ 連…
-
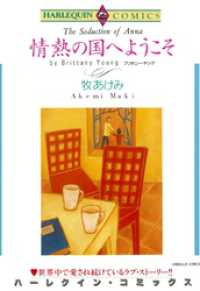
- 電子書籍
- 情熱の国へようこそ【分冊】 11巻 ハ…
-
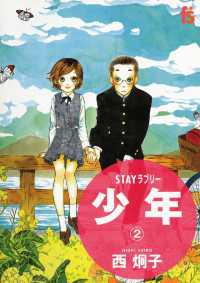
- 電子書籍
- STAYラブリー 少年(2) フラワー…
-

- 電子書籍
- アフタヌーン四季賞CHRONICLE …





