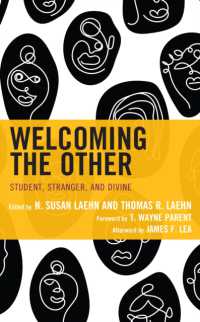出版社内容情報
イラストがひらく、教養としての教育学。「教える」とは何か、「学ぶ」とはどういうことか、教育の思想や歴史を軸に、教育原理のテキストとして基礎的な内容を概説。教育という営みのイメージをつかむことができる。教職を目指す学生の入り口として、また教養として教育学の世界に触れたい人にもおすすめの入門書。
内容説明
イラストがひらく教養としての教育学。教育原理入門の一冊。
目次
第1章 教育とは何か
第2章 教育の源流
第3章 教育の歴史
第4章 初期の教育と学習
第5章 教育学と実存哲学
第6章 教師と子どもの関係
第7章 実存と出会い
第8章 青年期の教育問題と防衛機制
第9章 日本の教育実践者たち
著者等紹介
広岡義之[ヒロオカヨシユキ]
1958年生まれ。神戸親和女子大学発達教育学部・同大学院教授。関西学院大学大学院文学研究科博士課程(教育学専攻)単位取得満期退学。博士(教育学)
北村信明[キタムラノブアキ]
1965年生まれ。きたむらイラストレーション(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
水生クレイモア(不見木叫)
12
教育史と教育学、入門書として興味深い(特に古代ギリシャ・ローマの教育史)。2023/01/16
Lagavulin
1
初めて教育学の本を読んだ。まとまりがないような気がした。頭に入ってこない。社会的成長か個人の成長、どちらを重視するのかは大事な視点だ。2023/09/24
seto4718
0
序盤ー中盤では古代ギリシアや中世〜近代の西洋哲学者・教育者達の主張に少しずつサラッと触れ、後半では教育実践の場でどのように振る舞うべきかについて紹介されていた。 イラストが登場人物のイメージを補強してくれたり、わかりにくい概念や例え話を翻訳してくれたりしたので、頭にスッと入ってきやすかった。 ソクラテス(希)やロジャーズ(米)、フロイト(澳)、林(日本)について特に共感・納得する場面があったため、また個別に本を読んでみたいと思った。2022/08/18
睦月
0
ほんとに教育学入門って感じでした。イラスト自体はとっつきやすいものの、中々本格的な内容でした。大学の教育学概論とかで習いそうな。一応最後まで目は通したけど興味がないところはあんまり頭に入ってこなかった。大学で教育学系もっととっておけば良かったと最近つくづく思う…2021/06/15
hiro taguchi(田口弘幸)
0
最近読んでいた教育関係の本と似たような内容が網羅されていた。さすが入門。従来のように連続性に適応できる積み上げ系教育(詰め込み教育)ばかりにならないように、予測のできない非連続性の事柄にぶち当たった時に乗り越えられる力を養うことに重きを置くようにしていくべし=非認知能力を高めること??西洋の哲学と建築様式の変遷が関連づけて捉えられていたのが個人的にとてもツボ。2021/01/08
-
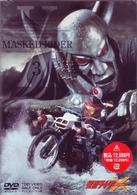
- DVD
- 仮面ライダーX Vol.3<完>