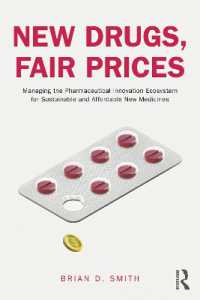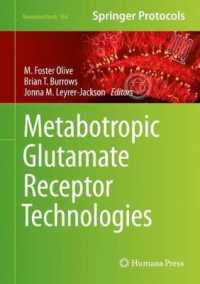出版社内容情報
ITC、自動運転、ドローン…… AIによる革新は日本をどう変えるか。効果と問題についての具体的な検証。人工知能(AI)が話題になっている。一方では技術革新がもたらす新たな生活への期待があり、もう一方では従来の仕事がなくなるという不安もあり、どう捉えるべきか難しい課題である。本書では、人工知能の登場が社会にどのようなインパクトを与えており、今後どうなっていくのか、経済学の知見を用いて検証する。自動車の自動運転など、喫緊の課題にも切り込んだ意欲作。
はじめに
序 章 人工知能は私たちの社会・経済にどのような影響を与えるのか?
1 AIの開発・普及の現状と今後
2 日本における有効的なAI活用・開発のための方策
3 AIが与える社会的な問題への対応
4 AIが与える影響のさまざまな分析の試み
第?部 AIの企業での活用とその課題
第1章 人工知能等が雇用に与える影響と社会政策
1 本章の内容
2 これまでの研究のレビュー
3 世界的なコンセンサスが得られた内容
4 ドイツの動向
5 日本の現場の動向
6 導出される社会政策
第2章 なぜ多くの企業がAIを経営に活用できないのか
1 企業がイノベーションを取り入れる3つの要因
2 技術要因
3 人 材
コラム AI経営における経営人材の役割
4 経営組織
5 外的要因
6 未来を創る
第3章 持続可能なスマートシティ実装
1 スマートシティの社会実装に向けて
2 スマートシティの実装評価方法に関する開発動向
3 共有価値創造による持続可能なスマートシティ実装評価モデルの検討
4 エネルギー・環境制約問題への実装評価モデルの適用事例??中之条電力「一般家庭の節電行動調査(デマンドレスポンス実証実験)」
5 経済・社会・環境が持続可能なスマートシティの実装評価モデル
第?部 AIに関する法的課題
第4章 AIの法規整をめぐる基本的な考え方
1 AIの法規整の機能的分析
2 分析のための状況設定
3 外部性への法による対処
4 AIのもたらす外部性への対処
5 AIと法
第5章 人工知能ビジネスの資金調達と法規制??クラウドファンディングを中心に
1 さまざまな資金調達手法
2 クラウドファンディングの歴史と分類
3 贈与型クラウドファンディングに対する法規制
4 購入型クラウドファンディングに対する法規制
5 融資型クラウドファンディングに対する法規制
6 エクイティ型クラウドファンディングに対する法規制
7 クラウドファンディング事業とそれに対する法規制の将来
第6章 ドローンと法??損害賠償の観点から考える
1 移動革命と損害賠償ルール
2 日本法における議論の前提
3 1952年のローマ条約およびその後の展開
4 米国の状況
5 米国以外の国々の主な動向
6 立法等の措置の必要性
7 損害賠償ルールの変更に伴う困難
第?部 AI の普及がもたらす影響
第7章 誰が自動運転車を購入するのか
1 問題の背景と研究目的
2 先行研究
3 調査概要
4 回答者の属性
5 自動運転車への支払意思額
6 自動運転は普及するのか
第8章 自動運転による自動車走行距離の変化
1 人工知能と自動車
2 走行距離推計モデル
3 分析に用いるデータの概要
4 自動運転の走行距離への影響の分析結果
5 自動運転導入による走行距離と温室効果ガス排出量変化
6 政策含意と今後の課題
第9章 情報技術の利用とマークアップの分析
1 情報技術とマークアップに関するこれまでの研究
2 トランスログ型生産関数によるマークアップの計測
3 データと推定方法
4 マークアップに関する実証分析の結果
5 情報技術の利用がマークアップに及ぼす影響
第10章 人工知能社会における失業と格差の経済理論
1 人工知能と雇用??これまでの研究
2 人工知能のサーチ理論的モデル
3 モデルの比較静学分析
4 外生変数の内生化
5 政策への示唆と今後の展望
第?部 AI技術開発の課題
第11章 労働時間が生活満足度に及ぼす影響??人工知能の活用方策に関する検討
1 日本人のワーク・ライフ・バランス
2 労働の非金銭的効果
3 データおよび推計方法
4 労働時間と生活満足度の関連性
5 人工知能の活用方策
第12章 日本企業のIT化は進んだのか??AI導入へのインプリケーション
1 日本の労働生産性の低迷
2 産業別IT投資
3 日本のIT導入の遅れに関する既存研究
4 企業レベルのIT投資??『企業活動基本調査』を使用した研究
5 IT投資は日本企業の生産性を上昇させる
第13章 情報化投資と法規制の影響??労働規制による資本投資及び情報化投資への影響の分析
1 労働規制の資本投資への影響
2 労働規制の資本投資、情報化投資への影響に関する先行研究
3 日本の労働規制の変化
4 分析に用いるデータ、及びモデル
5 労働規制の影響の分析結果
6 日本の雇用規制と新たな技術、情報化投資への影響の考察
第14章 人工知能技術の研究開発戦略??特許分析による研究
1 人工知能技術の研究開発について
2 いつ、どこで、どの技術が開発されたか?
3 どの出願者が、どの技術を開発しているのか?
4 どの出願者が、どこで特許を取得しているのか?
5 人工知能技術開発の研究戦略の変化
索 引
馬奈木 俊介[マナギ シュンスケ]
編集
内容説明
ITC、自動運転、ドローン…AIによる革新は日本をどう変えるか。効果と問題についての具体的な検証。
目次
人工知能は私たちの社会・経済にどのような影響を与えるのか?
第1部 AIの企業での活用とその課題(人工知能等が雇用に与える影響と社会政策;なぜ多くの企業がAIを経営に活用できないのか;持続可能なスマートシティ実装)
第2部 AIに関する法的課題(AIの法規整をめぐる基本的な考え方;人工知能ビジネスの資金調達と法規制―クラウドファンディングを中心に;ドローンと法―損害賠償の観点から考える)
第3部 AIの普及がもたらす影響(誰が自動運転車を購入するのか;自動運転による自動車走行距離の変化;情報技術の利用とマークアップの分析;人工知能社会における失業と格差の経済理論)
第4部 AI技術開発の課題(労働時間が生活満足度に及ぼす影響―人工知能の活用方策に関する検討;日本企業のIT化は進んだのか―AI導入へのインプリケーション;情報化投資と法規制の影響―労働規制による資本投資および情報化投資への影響の分析;人工知能技術の研究開発戦略―特許分析による研究)
著者等紹介
馬奈木俊介[マナギシュンスケ]
1975年生まれ。九州大学大学院工学研究科修士課程修了。米国ロードアイランド大学大学院博士課程修了(Ph.D.(経済学博士))。サウスカロライナ州立大学、横浜国立大学、東北大学などを経て、九州大学主幹教授・都市研究センター長。九州大学大学院工学研究院都市システム工学講座教授。東京大学客員教授、経済産業研究所ファカルティフェロー、地球環境戦略研究機関フェローを兼任。学術誌Economics of Disasters and Climate Change編集長、IPCC代表執筆者、IPBES統括代表執筆者、国連「新国富報告書2018」代表。専門:都市工学、経済学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おせきはん
takao
元吉