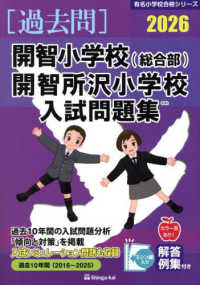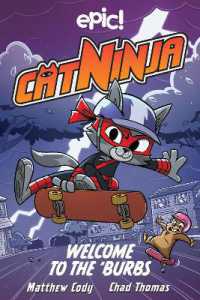出版社内容情報
語り、教育、政治、メディア・ミックス、海外展開、少女、食…マンガ・アニメで社会を読み解くための待望の道案内。マンガ・アニメで研究するとはいかなることなのか。表現論・作家論・作品論に偏ることなく、実社会との接点を重視した研究はいかになされるのか。マンガ・アニメを題材に論文を書きたいという国内外の学生が増える一方、現状の大学教育ではそれに対応できていない。本書では、マンガ・アニメで論文を書く際の「お手本」を学際的な観点から作り、学生や教員の一助となることを目指す。
はじめに
序 章 マンガ・アニメで研究するということ(山田奨治)
第I部 文化・社会からマンガ・アニメへ
第1章 語り──マンガ・アニメの伝統的コンテンツからの継承性(谷川建司)
1 何を明らかにするのか
2 『魔法少女まどか☆マギカ』
3 『JIN─仁─』
4 日本人の好むナラティヴの完成形としての「忠臣蔵」
5 結 論
コラム1 戦う文豪、闘う偉人──「異能バトル」作品からみる現在(飯倉義之)
第2章 形態──デジタル化時代のマンガと読者の生きられる時間(石田佐恵子)
1 時間の社会学から探求する「マンガと時間」
2 「連載」という作品発表形態の成立──マンガ雑誌と市場構造
3 「物語の中の時間」と「読者の生きられる時間」との関係
4 デジタル化時代のマンガと読者の生きられる時間
コラム2 マンガが社会と繋がるとき──〈3・11マンガ〉から考える(イトウユウ)
第3章 教育──子どもだけの世界における子どもの自律性・生命性・道徳(宮崎康子)
1 子どもだけの世界
2 自律性の獲得と人間形成の物語としての『漂流教室』
3 『7SEEDS』における未来に蒔かれた種としての子どもたち
4 子どもの自律性・生命性・道徳
コラム3 生命性の次元に触れる──五十嵐大介『海獣の子供』(宮崎康子)
第4章 政治──「伝記学習マンガ」を形作るもの(イトウユウ/山中千恵)
1 何を明らかにするのか
2 伝記学習マンガのタイトル選択傾向を分析する
3 伝記学習マンガの「表現」を分析する
4 「学習マンガ」と「伝記本」の親和性
5 結論──伝記学習マンガの〈政治性〉
第5章 近代性──産科医・助産師の活躍する“医療マンガ”(安井眞奈美)
1 少数派の立場から考える
2 産科医、助産師の活躍するマンガ
3 出産環境の近現代
4 医療マンガは何を物語っているのか
5 医療マンガの社会的意義
コラム4 メディアに描かれる子どもイメージ(宮崎康子)
第?部 マンガ・アニメから文化・社会へ
第6章 舞台──日本のアニメ・マンガと観光・文化・社会(岡本 健)
1 アニメ・マンガと観光の関係性
2 アニメ聖地巡礼とコンテンツツーリズム
3 アニメ・マンガ聖地における文化の伝達
4 コンテンツツーリズムに関わるコミュニケーション
5 観光コミュニケーションと文化創造
第7章 メディアミックス──そういうのもあるのか(横濱雄二)
1 メディアミックス
2 『孤独のグルメ』について
3 マンガ受容の広がり
4 井之頭五郎というキャラ
5 キャラと作品のメディアミックス
コラム5 フランスにおけるmangaの受容──影響、占有、周縁?(高馬京子)
第8章 海外展開──『るろうに剣心』の映画化とフィリピンでの人気(北浦寛之)
1 映画のヒットと海外展開
2 『るろうに剣心』の映画化
3 フィリピンでの人気
4 他のアニメは「剣心」に続けるか
コラム6 卒論テーマは「韓国でマンガが大人気」です!──それって、いつのどんなマンガの話?(山中千恵)
第9章 少女──フランス女性読者のアイデンティティー形成とキャラクターの役割(高馬京子)
1 何を明らかにするのか
2 フランスにおけるshojo受容の歴史的背景
3 フランスのメディア言説による追従すべき少女像の形成
4 フランス読者の言説により理想として形成されるshojoの少女像
5 結論にかえて
コラム7 英国新聞からみる日本の児童ポルノ問題──マンガ・アニメの記述を中心に(小泉友則)
第10章 食──ひとり飯にみる違和感と共感のゆくえ(西村大志)
1 食べることの滑稽さ──『かっこいいスキヤキ』
2 共感される自由なひとり飯──『孤独のグルメ』
3 共感から実用へ──『花のズボラ飯』
4 滑稽さへの回帰とネット時代の食マンガのゆくえ──『食の軍師』
第11章 言語──日本語から見たマンガ・アニメ(金水 敏)
1 何を明らかにしようとするか
2 役割語とは何か
3 物語の構造とアーキタイプ
4 アーキタイプと役割語
5 ケーススタディ──『風の谷のナウシカ』
6 研究法のまとめ
コラム8 「せんせい、ちょっと待っておれ!」──マンガ・アニメに牽引された日本語学習(山本冴里)
おわりに
マンガ・アニメ作品名索引
人名索引
山田 奨治[ヤマダ ショウジ]
2017年1月現在国際日本文化研究センター研究部教授(テレビ・コマーシャル研究)
内容説明
マンガ・アニメで研究するとはいかなることなのか。表現論・作家論・作品論に偏ることなく、実社会との接点を重視した研究はいかになされるのか。マンガ・アニメを題材に論文を書きたいという国内外の学生が増える一方、現状の大学教育ではそれに対応できていない。本書では、マンガ・アニメで論文を書く際の「お手本」を学際的な観点から作り、学生や教員の一助となることを目指す。
目次
第1部 文化・社会からマンガ・アニメへ(語り―マンガ・アニメの伝統的コンテンツからの継承性;形態―デジタル化時代のマンガと読者の生きられる時間;教育―子どもだけの世界における子どもの自律性・生命性・道徳;政治―「伝記学習マンガ」を形作るもの;近代性―産科医・助産師の活躍する“医療マンガ”)
第2部 マンガ・アニメから文化・社会へ(舞台―日本のアニメ・マンガと観光・文化・社会;メディアミックス―そういうのもあるのか;海外展開―『るろうに剣心』の映画化とフィリピンでの人気;少女―フランス女性読者のアイデンティティー形成とキャラクターの役割;食―ひとり飯にみる違和感と共感のゆくえ;言語―日本語から見たマンガ・アニメ)
著者等紹介
山田奨治[ヤマダショウジ]
1963年大阪府生まれ。1988年筑波大学大学院修士課程医科学研究科修了。1998年京都大学博士(工学)。現在、国際日本文化研究センター教授。総合研究大学院大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Chicken Book
左手爆弾
東雲そら
ゆずこ*
johnlenon64
-

- 洋書
- Derailed