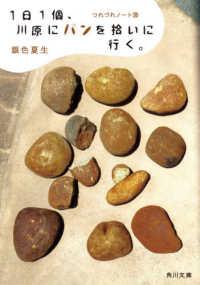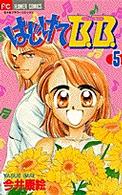出版社内容情報
一休・良寛らの名僧から漱石・?外らの文豪、現代の作家まで、文豪や名僧の筆蹟を読み解く![解説/外岡秀俊]歴史に名を刻んだ一休・良寛らの名僧から漱石・?外らの文豪、現代の作家まで、彼らが残した筆蹟はなにを物語るのか? 一点一画の〈筆蝕〉から書の本質に迫り、その人物像や現在までの書字の変遷をも浮き彫りにする![解説/外岡秀俊]
[序 書の風景]
?
最後の明治の臭気――坪内逍遙
墓碑銘――森?外
書家でない書――夏目漱石
褪色しない書きぶり――二葉亭四迷
時代の刻印――尾崎紅葉
滋味の書――幸田露伴
若さのきらめき――樋口一葉
筆先への心配り――泉鏡花
習書の痕――田山花袋
規矩の書――島崎藤村
行き届いた神経――芥川龍之介
平明と禁欲――有島武郎
枯 淡――有島生馬
湿った荒さ――里見?
無技巧の書――武者小路実篤
積木のように――志賀直哉
くすんだ世界――中里介山
悪戯の書――長谷川伸
普段着姿――佐藤春夫
粘液性の形象――川端康成
文字霊――中島敦
雑然の意味――太宰治
無頓着の書――坂口安吾
「無法書話」と書の行方――石川淳
?
難渋の印象――佐佐木信綱
戯れの書――清水比庵
なまめかしの美――尾上柴舟・吉沢義則
リフレーンの書――窪田空穂
時代の因習への挑戦――与謝野晶子
硬き古風――山川登美子
平明の書――会津八一
求道の書――斎藤茂吉
揮毫の旅――若山牧水
緩やかな流れ――北原白秋
和様とともに――吉井勇
造形の書――高村光太郎
書が似合わない――萩原朔太郎
原稿用紙によく映る――石川啄木
ペン書きの筆意――宮沢賢治
閑寂と思いやり――室生犀星
平易の書――堀口大学
幼な児のように――八木重吉
漢意への憧憬――三好達治
生の造形――吉野秀雄
書を楽しむ――草野心平
ペンの書――中原中也
?
古風から絶筆へ――正岡子規
下手な字讃歌――中村不折
情念の噴出――伊藤観魚
木簡からの啓示――河東碧梧桐
自然の書――高浜虚子
不定の形象――冨田渓仙
老境の書――荻原井泉水
書の間――中塚一碧楼
静かさと艶と――水原秋桜子
柔軟さの陰の硬質――山口誓子
「線」の形象――種田山頭火
淡々としたリズム――尾崎放哉
諧謔と執着――川端茅舎
良寛とともに――津田青楓
良寛への追慕――安田靫彦
苦心の書――村上華岳
初心の書――中川一政
絢爛の書――勅使河原蒼風
放射の書――岡本太郎
書への気負い――白井晟一
?
凄絶の来るところ――富岡鉄斎
書は美術ならず論争――岡倉天心
風雲の書――徳富蘇峰
古典への傾斜――内藤湖南
正統の論――長尾雨山
意志のリズム――西田幾多郎
流れへの傾き――津田左右吉
個的なものと運筆と――寺田寅彦
古風な影が――柳田国男
自己確認の書――河上肇
書が大嫌い――山川均
温和なたたずまい――和辻哲郎
粘りと穏やかさと――平塚らいてう
何の変哲もない――柳宗悦
書よりも論――福本和夫
死際の書――北一輝
解 説
[現代作家一〇〇人の字]
?
北村透谷――蛇行と直行
正宗白鳥――拙筆を自認
徳田秋声――たしかな骨格
鈴木三重吉/小川未明――規範からの遠心
永井荷風――複雑が生む魅力
谷崎潤一郎――光悦の臨書を日課
岡本かの子――ゆらぎの書
久保田万太郎――白き書
梶井基次郎――病的匂いなく
林芙美子――不馴れと馴れ
堀辰雄――大胆に軽やかに
吉川英治――王朝の書をモデルに
山本周五郎――いさぎよい書
松本清張――虚構の造形
江戸川乱歩――気難しい顔付き
海音寺潮五郎――鋭い切れ味
司馬遼太郎――陽性の書
?
大岡昇平――乾いた視線
野間宏――文字規範力の低下
武田泰淳――古典の淡き影
梅崎春生――暗澹の書
椎名麟三――鈍重の響き
島尾敏雄――書の造形の来るところ
深沢七郎――厭世と諷刺
福永武彦――揮毫の功罪
吉行淳之介――退嬰と揶揄と
安部公房――ジャンルの越境
三島由紀夫――温感の書
立原正秋――速度だけが虚ろに
水上勉/藤本義一/五木寛之――運筆の快感
野坂昭如――ペン書きの時代に
開高健――「筆ペン」の限界
大岡信――「書は人なり」ということ
大江健三郎――書の終焉
瀬戸内寂聴――墨痕のクレバス
田辺聖子――女の表情
星新一――習字でノイローゼ克服
筒井康隆――硬筆の手さばきで
井上ひさし/山藤章二――当世「丸文字」風
?
土井晩翠/竹久夢二――〈流れ〉と〈流れ〉の喪失
島木赤彦――きまじめな書
釈迢空――情念のうねり
滝井孝作――書き馴れた眼
中村草田男/加藤楸邨/石田波郷――粒立つ文字
西脇順三郎――毛筆の現代詩
小野十三郎――詩と書の変容
萩原恭次郎――視覚詩と書
吉田一穂――点と線
高橋新吉――率意の滋味
立原道造/島木健作――活字と書
吉本隆明――植え込まれる文字
谷川雁――自筆詩集
武満徹――点と音
谷川俊太郎――文字と磁場
?
小川芋銭/小川千甕――飄逸の書
吉川霊華――やや古風な流れ
北大路魯山人――穏潤の書
熊谷守一――淡き書
河井寛次郎――群魂の書
富本憲吉――炎を見る者
棟方志功――肉筆の板画文字
東山魁夷――基本に忠実
鏑木清方――心にくいばかり
横尾忠則――異邦人の視線
長谷川町子――サザエさんの文字学
?
副島種臣――構図の発見
犬養毅――『木堂翰墨談』
野上弥生子――硬質の骨格
亀井勝一郎――墨蹟の匂い
唐木順三――「戒語」の書
福田恆存――膠着の書
保田與重郎――文人の書
小林秀雄――贋作と美の価値
吉川幸次郎――伝統の面影
白川静――文字学の現在
花森安治――クレヨン文字
糸井重里――現代若者文字
?
中上健次――危険な接点
吉増剛造――速度感と成熟
荒木経惟――悩ましき字
椎名誠――書の終焉の中で
俵万智――不思議な符合
吉本ばなな――作家とワープロ
望月通陽――人形のような線
ビートたけし――バランスの良いサイン
現在の書を分類する
?林真理子/宮城谷昌光――習字モデル派
?山田詠美/宮部みゆき――丸文字派
?村上春樹/篠原ともえ――イラスト文字派
?大沢在昌――現在の無頼派
「酒鬼薔薇聖斗」――悲しい闘争宣言
[名僧の書――歴史をつくった五〇人]
はじめに
第一章 建国・擬似中国時代の僧――国づくりを担った七人
奈良写経――国づくりの書
鑑真・恵雲――王羲之立国・日本
道鏡――抽斗の多い書
最澄・空海――比叡山と高野山
空海――もうひとつの顔
円珍――万葉仮名から女手へ
第二章 日本文化確立時代の僧――日本仏教を拓いた八人
西念――片仮名の歌
西行――新古今時代の古今思慕
法然――粘りと切れと覚悟
栄西・俊?――黄庭堅の書の衝撃
親鸞・恵信尼――茫洋と逆説
明恵――線の太さと信仰の強靭
第三章 大陸からの亡命僧とその影響――政治と学問に勤しんだ一六人
道 元――圭、直、振幅
蘭溪道隆・無学祖元――二人の亡命僧の力
日蓮――異形の書
円爾・癡兀大慧――末期の書の魅惑
一山一寧・雪村友梅――大陸の自信、弧島の律儀
宗峰妙超――墨蹟の和様化
夢窓疎石・義堂周信・絶海中津――大陸の書との遠近
大智――黄庭堅の謙虚な学習
一休宗純――墨蹟の変質
古嶽宗亘・一絲文守――月と団子そして龍、異界への通路
第四章 政教分離後の僧――表現へと向かう一九人
以心崇伝・天海――法的な骨と優柔の肉
藤原惺窩・林羅山――鮮やかな気どりと、変哲なき書きつけ
沢庵宗彭・江月宗玩――苦と憂いと
清巌宗渭――一行書
隠元隆?・即非如一――近世墨蹟の行手を暗示
契沖――学の繊細
白隠慧鶴――書ならざる書
寂厳――伸縮自在のからくり細工
慈雲飲光――筆蝕の直接性と不立文字
風外慧薫・東嶺円慈・妙喜宗績――三つの奇書
仙?義梵――円相・方相・三角相
良寛――自省する筆蝕、批評する書
蓮月尼――「刻り」と「距離」の近代性
凡 例
解 題
解 説 書の透視図法(外岡秀俊)
石川 九楊[イシカワ キュウヨウ]
書家・評論家
内容説明
歴史に名を刻んだ一休・良寛らの名僧から漱石・鴎外らの文豪、現代の作家まで、彼らが残した筆蹟はなにを物語るのか?一点一画の“筆蝕”から書の本質に迫り、その人物像や現在までの書字の変遷をも浮き彫りにする!
目次
序 書の風景(最後の明治の臭気―坪内逍遥;墓碑銘―森鴎外;書家でない書―夏目漱石 ほか)
現代作家一〇〇人の字(北村透谷―蛇行と直行;正宗白鳥―拙筆を自認;徳田秋声―たしかな骨格 ほか)
名僧の書―歴史をつくった五〇人(建国・擬似中国時代の僧―国づくりを担った七人;日本文化確立時代の僧―日本仏教を拓いた八人;大陸からの亡命僧とその影響―政治と学問に勤しんだ一六人 ほか)
著者等紹介
石川九楊[イシカワキュウヨウ]
1945年福井県越前市生まれ。京都大学法学部卒業。京都精華大学教授、同大学文学文明研究所所長等を歴任。現在、書家、評論家、京都精華大学客員教授。主著『書の終焉』同朋舎出版、1990年、サントリー学芸賞受賞。『日本書史』名古屋大学出版会、2001年、毎日出版文化賞受賞。『近代書史』名古屋大学出版会、2009年、大佛次郎賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。