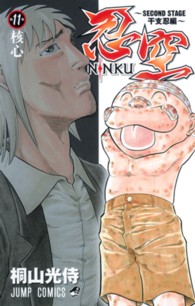内容説明
社会福祉理論・歴史研究に加え、保育、女性、障害者、高齢者…と実に幅広い分野を切り拓き、生活権保障を追究してきた一番ヶ瀬康子。一番ヶ瀬が今日の社会福祉研究に与えた影響は計り知れない。本書は、この一番ヶ瀬の社会福祉論を多面的な角度から再検討する。
目次
第1章 一番ヶ瀬康子の研究系譜と社会福祉教育
第2章 一番ヶ瀬社会福祉学の成立と意義―戦後社会福祉学研究の転機
第3章 社会福祉における「学」の成立と「科学」性―一番ヶ瀬『運動論』の位置
第4章 社会福祉の生活理論
第5章 社会福祉史研究の視点と方法
第6章 社会福祉と社会政策―ミクロとマクロの交差
第7章 一番ヶ瀬社会福祉論と現代児童福祉の指標
第8章 女性福祉への視点―自分史からの探究
第9章 一番ヶ瀬福祉学における障害者問題研究
第10章 一番ヶ瀬社会福祉と介護福祉論
著者等紹介
岩田正美[イワタマサミ]
1971年中央大学大学院経済学研究科修士課程修了。1994年博士(社会福祉学)。現在、日本女子大学人間社会学部教授
田端光美[タバタテルミ]
1955年日本女子大学家政学部社会福祉学科卒業。2004年博士(社会福祉学)。現在、日本女子大学名誉教授
古川孝順[フルカワコウジュン]
1941年東京都立大学大学院人文科学研究科修士課程修了。1994年博士(社会福祉学)。現在、西九州大学健康福祉学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆう。
7
社会福祉研究ではかかせすことのできない、一番ヶ瀬先生の理論を再検討した研究書です。論者によって、一番ヶ瀬先生への評価が微妙に異なりますが、社会福祉理論から児童、女性、障害、介護の各論まで、幅広く学ぶことができます。僕が思ったのは、この本で一番ヶ瀬先生をわかった気持ちになってはならないこと。一番ヶ瀬先生を直接読み、学ばないといけないと強く感じました。また、一番ヶ瀬先生が、生活問題を社会福祉の対象とされていることは周知の事実ですが、一貫して生活概念を深めようとしていたことが、この本から学べました。2014/03/18