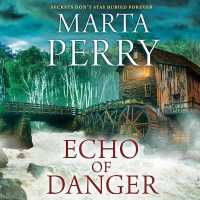内容説明
地域福祉の視点からケアを再検討。要支援者を排除しないケアリングコミュニティとは。全国の先駆的な実践からそのあり方と方法を考察。
目次
第1部 理論課題編(ケアと福祉文化―ケアリングコミュニティづくりの思想と文化;ナイチンゲール思想とケアの本質―コミュニティケアを担う人材育成への道;孤立を生み出す社会から互いに支え合う社会へ―新たなサポートシステムの構築に向けて;ケアリングコミュニティの構築に向けた地域福祉―地域福祉計画の可能性と展開;ケアとユニバーサルデザイン―ユニバーサルデザインで地域共生社会を目指す ほか)
第2部 実践編(小地域コミュニティにおける主体形成・実践―超高齢化地域とケアリング実践;社会福祉施設の再編とケアリングコミュニティづくり―ケア付き住宅からケア付きコミュニティへ;障害、高齢、児童の共生デイサービス―富山県「このゆびとーまれ」の実践;終末期の高齢者ホームにおける家族参加の介護・看取り―新潟県からし種の家とマナの家の実践;市民と行政のパートナーシップ―福祉21ビーナスプランの挑戦と実践 ほか)
著者等紹介
大橋謙策[オオハシケンサク]
1943年生まれ。1973年東京大学大学院教育学研究科博士課程満期修了。現在、日本社会事業大学名誉教授。東北福祉大学大学院特任教授。(公財)テクノエイド協会理事長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆう。
13
ケアを地域福祉の視点からとらえた本です。内容は理論編と実践編と大きく二つにわけられています。ここでは、ケアリングコミュニティという概念が提示されます。それは、福祉サービスを必要とする人を社会的に排除するのではなく、地域社会の一員として包摂し、日常生活圏域の中で支えていけるようにすることだと説明されています。クライエントの地域で思いを最大限尊重するのは、その人の生の尊厳を守るうえで大切です。しかし、社会的排除や包摂という概念が、政府のいう共助の概念で捉えられているのが少し疑問に思いながら読みました。2014/12/26