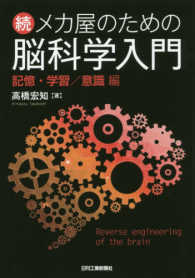目次
第1部 アタッチメント研究で使うアセスメントの臨床利用(母子の関係性を形成するための治療計画―子どもに対する作業モデルインタビューを臨床的に応用して;子どもの内的世界を心に留めておけること―治療的幼稚園における母親への洞察力とアセスメント;虐待された子どもとその養親に対する治療的介入―アタッチメント関係を促進する行動を特定していく;里親ケアにおける養育責任者としての役割―「この子は私の赤ちゃん」インタビューからの洞察;子どもの診断に関する親の解決と親子関係―「診断への反応インタビュー」~の洞察)
第2部 アタッチメント理論と心理療法(アタッチメントとトラウマ―家庭内暴力にさらされた幼い子どもを治療するための統合的アプローチ;サークル・オブ・セキュリティという取り組み―事例研究:“自分がもらえなかったものを与えることはつらいよね”;子どもの不健全な内的作業モデルに変化を起こす―治療的幼稚園においてアタッチメントを基礎とする治療方略を用いて;未組織型の母親と未組織型の子ども―感情の調整が不全な状態での心理化と治療によってもたらされる変化)
著者等紹介
オッペンハイム,ダビッド[オッペンハイム,ダビッド][Oppenheim,David]
博士。イスラエルのハイファ大学の心理学科の准教授であり、Infant Mental Health Journalの共同編集者である。20年以上にわたってアタッチメント研究を続けてきており、子どもの発達や精神衛生にとって、安定した情緒的に開かれた親子の関係性がいかに重要であるかということに焦点を当てている。子どもの内的世界に対する親の洞察力によって、どのように安定したアタッチメントが発達するのかについて研究したり、また、臨床群の研究にアタッチメントの概念や方法を応用したりしてきた。アタッチメントの臨床応用について活発に講義を行ったり、執筆したりしている
ゴールドスミス,ドグラス・F.[ゴールドスミス,ドグラスF.][Goldsmith,Douglas F.]
博士。認定された臨床心理士であり、ユタ州ソルトレイク市にある子どもセンターの常任理事である。子どもセンターは乳児期から就学前までの子どもを持つ家族に対する治療を専門としている。専門はアタッチメントの問題に対するアセスメントと治療で、アタッチメント理論の臨床実践への応用について、いくつかの論文を執筆している。ユタ大学の教育心理学科、心理学科、精神医学科における非常勤講師も務めている
数井みゆき[カズイミユキ]
茨城大学教育学研究科教授。メリーランド大学大学院応用発達心理学専攻、心理学PhD.(1991年)。乳幼児のアタッチメントと親のアタッチメント表象の関連を、夫婦関係、家族関係、社会的サポート、およびストレス等との関連で検討してきた。その後、乳児院入所児対象のアタッチメントとトラウマと発達全般の研究を行ってきた
北川恵[キタガワメグミ]
甲南大学文学部准教授、臨床心理士。京都大学博士(教育学)(2001年)。関係性に基づく人格発達の理解とアセスメントに関する研究、発達研究知見と心理臨床の橋渡しに関する理論的・実践的研究に取り組んでいる。特に、様々なリスク(発達障害、不適切な養育経験など)を抱える親子への関係性支援に関心がある。アタッチメント理論に基づく親子関係支援プログラムである、サークル・オブ・セキュリティを日本で実践している
工藤晋平[クドウシンペイ]
広島国際大学心理科学部講師。九州大学大学院人間環境学府人間共生システム専攻、博士(心理学)(2006年)。精神科臨床における精神分析的心理療法に長く携わり、その中でAAIを始めとする成人のアタッチメント研究の成果を取り入れる試みをしてきた。現在、新しい測定法によるアタッチメント表象の研究とその臨床適用を始めている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。