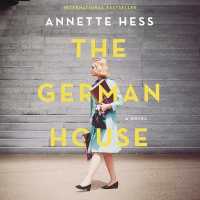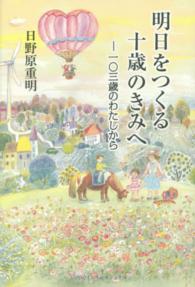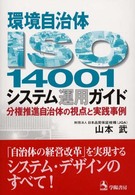内容説明
紀貫之(きのつらゆき、八七二頃~九四六)平安期の歌人。『古今和歌集』編纂や『土佐日記』執筆で知られ、また膨大な和歌を『貫之集』として残す平安歌人、紀貫之。本書では、貫之の言葉を読み込むことにより、その多彩なフィクションの問題を明らかにする。フィクションとしての屏風歌、フィクションとしての歌・物語、フィクションとしての日本語、そしてフィクションとしての人生…。
目次
第1章 『古今和歌集』仮名序―あまりに普遍的な和歌観
第2章 『貫之集』―はじめに屏風歌あり
第3章 『貫之集』―恋歌・雑歌の世界
第4章 『貫之集』―土佐守以降の歌風
第5章 貫之の『伊勢物語』体験
第6章 『土佐日記』―言葉と死
第7章 仮名表記の思想
終章 『新撰和歌集』漢文序―本音としての漢文
著者等紹介
神田龍身[カンダタツミ]
1952年山梨県甲府市生まれ。現在、学習院大学文学部日本語日本文学科教授。研究テーマは、日本古典文学における“書くこと”(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヨグ=ソトース
7
神田先生曰く「これが一番(笑)」な紀貫之考。講義内容は主に第六章に凝縮。『土佐日記』における海面上の虚像が貫之の言語観の喩的表現であることは講義の中で最大のテーマとして扱われていた通り。本書では屏風歌歌人としての経歴や土佐守以降の歌の傾向にまで考察が及んでいる。『伊勢物語』(貫之作者説)と『古今集』の比較は面白かった。例示を重ね、コンテクストこそが歌の意味を決定することに貫之が気付いていた可能性を丁寧に探っている。2019/01/11
そーだ
0
参考文献に「読書案内」と称して著者のコメントが付されており、次の読書を促していることに好感が持てる。2010/02/23
エイジ
0
研修でお話を聞きました。その時、「今話した内容を本にしています」と話されていたので、ずっとチェックしていました。2009/11/21
-

- 和書
- サザエさん事典