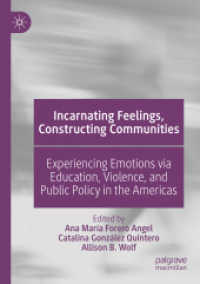出版社内容情報
【内容】
矛盾と緊張関係を孕む「近代スポーツ」とは
本書はスポーツを複眼的・包括的に理解しようとして近代における歴史的・社会的存在としてのスポーツの個性を多面的に探究していく。
本書の第1部では、国民国家形成過程における国民的・民族的アイデンティティの強化や文化を媒介とした国民統合とスポーツとの関係、およびスポーツの階級的性格と道徳的・規範的意味の付与の実態などが問題とされる。第2部では、人びとのエネルギー集積の場としての民衆娯楽や祭典が、権力や権威そして支配秩序との関係において同化ないし周辺化され、あるいは淘汰・解体されていく状況と、それとは逆に独特な共同の時空を生みだすことでスポーツにおける主体性形成の拠点を形成していく状況が論じられる。第 部では、国境を越えるスポーツを巡る国家間の緊張関係と国際政治とリンケージしたスポーツあるいはスポーツイベントのグローバルな展開過程が検討される。
【目次】
はしがき
第1部 近代国民国家の形成とスポーツ
第1章 ジェントルマン・アマチュアとスポーツ
――19世紀イギリスにおけるアマチュア理念とその実態(池田恵子)
1 「アマチュア神話」検証の旅
2 社会的コンセンサスとしてのアマチュア神話
3 プロフェッショナルの容認
4 避けがたい神話の結論
[コラム]レディース・アマチュア
第2章 身体への近代的まなざし
――フランス文学にみる身体観・スポーツ観(小石原美保)
1 体操の女神――身体鍛練の正当化
2 スポーツとモデルニテ
3 スポーツ文学における身体へのまなざし
[コラム]試合という物語
第3章 ソコルと国民形成
――チェコスロヴァキアにおける体操運動(福田 宏)
1 デモクラシーの学校
2 国民的組織としてのソコル
3 ソコル創設期におけるチェコ人
4 チェコ人、そしてスラヴ人の連帯へ
5 「国民」の枠をはみ出す人々
6 これからのソコル
[コラム]ハプスブルク帝国とオリンピック――チェコ人の参加をめぐって
第2部 スポーツと民衆
第4章 失われた民衆娯楽
――イギリスにおけるアニマル・スポーツの禁圧過程(松井良明)
1 失われた民衆娯楽
2 全工業化時代のアニマル・スポーツ
3 動物虐待防止法の成立
4 アニマル・スポーツの撲滅に向けて
5 祝祭からレジャーへ
[コラム]スポーツと賭博――賭博スポーツとしての闘鶏
スポーツと祝祭――シュロヴタイドのフットボール
第5章 西南ドイツにおけるトゥルネン協会運動
――1840年代のシュヴァーベンを中心に(有賀郁敏)
1 ある地方新聞の記事から
2 トウゥルネン協会の成立と組織の理念
3 ラントトゥルネン祭の諸相
4 トゥルネン協会における諸会議
5 トゥルネン協会と女性
[コラム]トゥルネン協会と自主消防団
第6章 チェコスロヴァキアの人民スポーツ運動
――その位置づけに関する一試論(功刀俊雄)
1 なぜチェコスロヴァキアなのか
2 「『フェア・プレー』運動」の変遷(1)
――ベルリン・オリンピック反対運動
3 「『フェア・プレー』運動」の変遷(2)
――民衆のためのスポーツ改革運動
4 「オフィシャルな」スポーツ組織との結びつき
[コラム]歴史の見直し?
第3部 スポーツの国際関係
第7章 近代オリンピック前史
――近代ギリシャ人によるオリンピック復興(真田 久)
1 古代ギリシャへの回帰
2 古代オリンピック復興への序章
3 古代オリンピックの復興
4 オリンピア競技祭の展開
[コラム]ギリシャ人とクーベルタンとの対立
第8章 フィールドのオリエンタリズム
――K・S・ランジットシンとわれわれの帝国(石井昌幸)
1 大英帝国とクリケット
2 K・S・ランジットシンとラージマル・コレッジ
3 イギリスでの日々
4 「ランジ」を語る
5 藩王ランジットン
[コラム]メリルボーン・クリケット・クラブと女性
境界を越えて
第9章 オリンピック大会を自然死させよ!
――戦前二つのオリンピックをめぐるイギリス協調外交(青沼裕之)
1 オリンピック運動とスポーツ史研究の課題
2 1936年ベルリン大会までのイギリス外務省の既定方針
3 1940年大会のロンドン招致の運動とイギリス外務省の介入
4 1940年大会の東京開催をめぐる論争とイギリス外務省の思惑
5 何を課題として残したか
[コラム]イギリスの反ナチ・スポーツ運動
補 論 グローバリゼーションとスポーツ
――ノルベルト・エリアス、ジョセフ・マグワィアの描く像
(山下高行)
1 「文明化の過程」とグローバリゼーション
2 グローバル化するスポーツ
3 グローバル化するスポーツの描き方
文献解題
内容説明
本書は、スポーツを複眼的・包括的に理解しようと、近代における歴史的・社会的存在としてのスポーツの個性を多面的に探究していく。第1部では、国民国家形成過程における国民的・民族的アイデンティティの強化や文化を媒介とした国民統合とスポーツとの関係、およびスポーツの階級的性格と道徳的・規範的意味の付与の実態などが問題とされる。第2部では、人びとのエネルギー集積の場としての民衆娯楽や祭典が、権力や権威そして支配秩序との関係において同化ないし周辺化され、あるいは淘汰・解体されていく状況と、それとは逆に独特な共同の時空を生みだすことでスポーツにおける主体性形成の拠点を形成していく状況が論じられる。第3部では、国境を越えるスポーツを巡る国家間の緊張関係と国際政治とリンケージしたスポーツあるいはスポーツイベントのグローバルな展開過程が検討される。
目次
第1部 近代国民国家の形成とスポーツ(ジェントルマン・アマチュアとスポーツ―一九世紀イギリスにおけるアマチュア理念とその実態;身体への近代的まなざし―フランス文学にみる身体観・スポーツ観 ほか)
第2部 スポーツと民衆(失われた民衆娯楽―イギリスにおけるアニマル・スポーツの禁圧過程;西南ドイツにおけるトゥルネン協会運動―一八四〇年代のシュヴァーベンを中心に ほか)
第3部 スポーツの国際関係(近代オリンピック前史―近代ギリシャ人によるオリンピック復興;フィールドのオリエンタリズム―K・S・ランジットシンとわれわれの帝国 ほか)
補論(グローバリゼーションとスポーツ―ノルベルト・エリアス、ジョセフ・マグワィアの描く像)