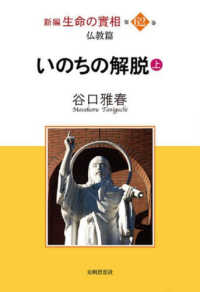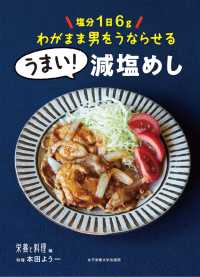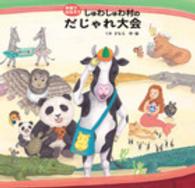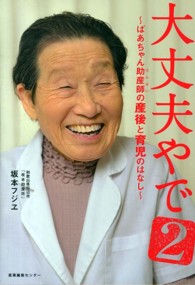内容説明
フランドル地方ほど典型的に「中世都市」が発展した地域はないといわれている。本書では、中世フランドル都市の生成・成長の問題を、在地経済・在地社会との関係から明らかにする。そして、在地住民が織りなす多層的な商品流通世界にスポットをあて、諸侯権力と初期都市民とのかかわりも問題にする。
目次
序章 問題の所在と本書の構成
第1章 フランドルにおける大都市の生成とその複合要因―イープルの初期発展をめぐる研究史
第2章 フランドルにおける修道院都市の発展と年市―中小都市メーゼンの場合
第3章 フランドル年市の古層的系譜―ヘントの聖バヴォ年市を中心に
第4章 フランドル都市の初期発展と農業的基盤―飢饉に関するガルベルトゥスのテキストと学界論争
第5章 フランドル都市経済の在地流通的基盤―都市ヘントと周辺都市に関する流通税表の相互比較分析
第6章 フランドル都市経済における地域連関の生成―流通税表を素材としてみたスヘルデ河流域のニシン流通を中心に
第7章 フランドル都市経済と生活物資商品化の諸過程―都市サン・トメールの流通税表をめぐる層位学的考察
第8章 フランドル都市の成長とインフラストラクチャー―新港建設と干拓事業をめぐる研究史
終章 フランドルにおける都市・流通・権力―フランドル伯の行為とその限界
著者等紹介
山田雅彦[ヤマダマサヒコ]
1957年島根県出雲市に生まれる。1980年九州大学文学部卒業。1985年九州大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。1986年ベルギー・ヘント大学に留学(~88年)。1989年熊本大学文学部史学科に赴任(講師)。現在、熊本大学文学部歴史学科教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
人生ゴルディアス
人生ゴルディアス