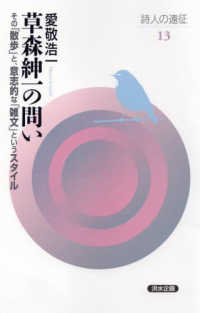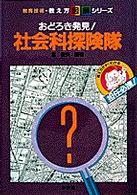出版社内容情報
【内容】
1980年代の中頃から世界的な市場経済化、グローバル化が急速に進行してきたが、グローバル化といっても様々の位相があり、今なお進行中の事態である。グローバル化は、当然のことながら発展途上国や移行経済諸国の市場経済化や経済改革、開放政策の推進などが前提となっており、さらにはリージョナル化(地域的な経済統合)の進行もめざましい。グローバル市場経済を一面的に捉えることは不可能である。本書では各分野の専門研究者による多角的・多面的なアプローチによる分析を行い、グローバル市場経済の実相に迫る。
【目次】
まえがき
序 章 グローバル市場経済の進展とその位相
――貿易・投資・地域主義(嶋田 巧)
第1部 グローバル市場経済化の基軸
第1章 現代アメリカ通商政策とアジア
――地域主義をふくむ通商政策の展開(小野塚佳光)
第2章 国際通貨制度への「市場メカニズムの浸透」
――国際通貨制度からみた「金融のグローバル化」の意味(平 勝廣)
第2部 グローバル市場経済化の諸断面
第3章 「円キャリー・トレード」と国際通貨金融危機
――グローバリゼーション下の日本の金融経済(鳥谷一生)
第4章 東アジアの貿易・投資と日本企業の競争戦略(田中武憲)
第5章 韓国企業のアジア展開
――輸出拡大から生産拠点の展開へ(服部民夫)
第6章 中国における企業改革と社会保障制度改革
――企業・労働者の位置づけの変遷を中心に(横井和彦)
第7章 「新興市場」インドにおけるマクロ経済政策(佐藤隆広)
第8章 インドの経済自由化と農村労働市場
――農業労働市場統合分析(宇佐美好文・角井正幸)
第9章 イギリスにおける単一通貨導入問題(松浦一悦)
索 引
内容説明
本書は、グローバル市場経済化の全体に関わる問題の所在を論じた序章についで、第1部には、グローバル市場経済化を主導してきたアメリカの通商政策と国際通貨制度からみた金融のグローバル化の意味を解明した論考を、第2部には、主に、金融グローバル化のなかの日本の現実と、エマージング・マーケットとして、この間のグローバル市場経済化の最先端に位置し、めざましい経済成長から一転して通貨・金融危機の波濤に飲み込まれたアジア地域を取り上げた諸論考をおさめている。
目次
グローバル市場経済化の進展とその位相―貿易・投資・地域主義
第1部 グローバル市場経済化の基軸(現代アメリカ通商政策とアジア―地域主義をふくむ通商政策の展開;国際通貨制度への「市場メカニズムの浸透」―国際通貨制度からみた「金融のグローバル化」の意味)
第2部 グローバル市場経済化の諸断面(「円キャリー・トレード」と国際通貨金融危機―グローバリゼーション下の日本の金融経済;東アジアの貿易・投資と日本企業の競争戦略;韓国企業のアジア展開―輸出拡大から生産拠点の展開 ほか)
著者等紹介
平勝広[ヒラカツヒロ]
1944年生まれ。1967年九州大学経済学部卒業。九州大学大学院経済学研究科を経て、現在、同志社大学商学部助教授。主著に『最終決済なき国際通貨制度―「通過の商品化」と変動相場制の帰結―』日本経済評論社、2001年。『金融論―理論・歴史・政策―』(共著)ミネルヴァ書房・1995年
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。