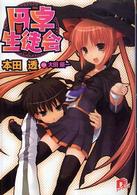出版社内容情報
【内容】
第一巻は著者が生前すでに作成していた編集プランに沿うものである。日本の多くの社会制度と同様に、日本の貨幣制度の変転も常に外からやってきた。遅れて世界市場に参加した日本は、アングロサクソンの国際通貨環境の論理に合わせざるをえなかった。近代化に乗り出す日本が、貿易に重要な安定した通貨を支配できなかった事情を検証し、貿易銀貨流通の努力の失敗、金本位制の採用から国際通貨秩序に合わせ変革していく日本の、絶えざる自己改革の軌跡を論考する。
【目次】
まえがき
第1章 日本におけるメキシコドルの流入とその功罪
1 洋銀(メキシコドル)
2 開港と洋銀の流入
3 金貨の流出
4 幣制の改革
5 洋銀相場の問題
むすび:洋銀の功罪
第2章 日本における近代的貨幣制度の成立とその性格
――初期幣制と洋銀(メキシコドル)との交渉
1 幣制改革の端緒
2 初期本位制案
3 新貨条例の性格と日本貿易銀
4 兌換銀本位制の成立
第3章 東亜におけるメキシコドルの終焉
1 東亜におけるメキシコドルをめぐる角逐とその本質
2 東亜におけるメキシコドル終焉の過程
3 東亜におけるメキシコドル終焉の論理
第4章 日本における金本位制の成立過程
1 日本における金本位制の成立(1)
2 日清戦争賠償金の領収と幣制改革:日本における金本位制の成立(2)
3 添田プランと高橋意見書:明治30年貨幣法案の準備過程
補論1 国際金融――貨幣制度の国際的関連を中心として
問題の限定
1 国際金本位制成立の論理
2 金本位制の成立効果(1):とくに国際分業効果に関連して
3 金本位制の成立効果(2):古典派的テーゼの検討
4 金本位制にたいする反論:ケインズを中心として
5 金為替本位制の展開と本質
6 再編金為替本位制の性格:国際通貨基金をめぐって
補論2 メキシコドルの終焉に関する鬼頭教授の遺稿について
補論3 金解禁の動因について
――野呂栄太郎の金解禁論をめぐって
編集後記
内容説明
第一巻は著者が生前すでに作成していた編集プランに沿うものである。日本の多くの社会制度と同様に、日本の貨幣制度の変転も常に外からやってきた。遅れて世界市場に参加した日本は、アングロサクソンの国際通貨環境の論理に合わせざるをえなかった。近代化に乗り出す日本が、貿易に重要な安定した通貨を支配できなかった事情を検証し、貿易銀貨流通の努力の失敗、金本位制の採用から国際通貨秩序に合わせ変革していく日本の、絶えざる自己改革の軌跡を論考する。
目次
第1章 日本におけるメキシコドルの流入とその功罪
第2章 日本における近代的貨幣制度の成立とその性格―初期幣制と洋銀との交渉
第3章 東亜におけるメキシコドルの終焉
第4章 日本における金本位制の成立過程
補論1 国際金融―貨幣制度の国際的関連を中心として
補論2 メキシコドルの終焉に関する鬼頭教授の遺稿について
補論3 金解禁の動因について―野呂栄太郎の金解禁論をめぐって
著者等紹介
小野一一郎[オノカズイチロウ]
1925年10月10日大阪市に生まれる。1945年京都帝国大学経済学部入学。1949年卒業(この間、1944年12月入隊、中国大陸派遣、1946年2月本土帰還)。大阪銀行(現在住友銀行)、大阪市研究員・大阪市立大学経済研究所勤務を経て、1951年京都大学経済学部助手。講師、助教授を経て、1970年京都大学経済学部教授。経済学部長・大学院経済学研究科長を歴任。1989年京都大学退官、京都大学名誉教授。同年阪南大学商学部教授。阪南大学図書館長(1991・4~1993・3)。1996年阪南大学退職。1996年12月7日永眠。勲二等瑞宝章正四位を受ける。編著書に『ブラジル移民実態調査』有斐閣、1955年。『世界経済と帝国主義』(共編)有斐閣、1973年。『南北問題入門』(共編)有斐閣、1979年。『両大戦間期のアジアと日本』(共編)大月書店、1979年。『南北問題の経済学』同文館出版、1981年。『戦間期の日本帝国主義』世界思想社、1985年。『国際流通とマーケティング』(共監修)同文館出版、1992年。『日本貿易の史的展開』(日本貿易史研究会編)三嶺書房、1997年。訳書にM.ドッブ『後進国の経済発展と経済機構』有斐閣、1956年。A.I.ブルームフィールド『金本位制と国際金融1880-1914』(共訳)日本評論社、1975年。以上の他に、学術論文約90、調査、辞典項目執筆、その他多数
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。