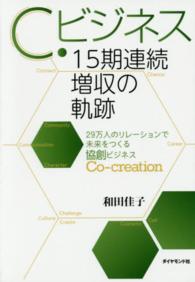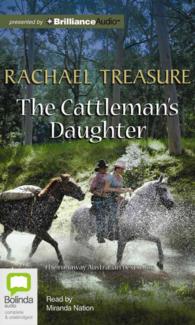出版社内容情報
【内容】
2002年に向けた教育課程の改訂は現在の競争主義的教育を改革するどころか、学校の多線化を押し進め、「個性化」や「多様化」は、実は統制された学習した生み出さない。本書は、現在の中教審・教課審の構想する学校スリム化論のもとで、教育水準の縮減もなく、国民的共通教養論とも異なる多文化的「共生の教養」を土台とする構想を提示する。また、競争的で統制的なこれらの学びに抗して、批判的で共同的な関係の授業や、学びをつくる観点から、新たな授業づくりを構想する。
【目次】
第1章 多線形学校の誕生――中教審答申批判
第2章 教育審議会答申の基本問題
第3章 多文化的共通教養論
第4章 授業の転換――共同する社会科をめぐって
第5章 相互主体関係における指導性
第6章 学びへの参加権
第7章 歴史の学力形成と「自分の知識」
第8章 支配される学びと表現する学び
第9章 学びにおける明晰な政治
第10章 教科内容研究の真理性と政治性への転回
第11章 ディベート・発表学習・ワークショップ
第12章 総合学習の存在と教育課程づくり
内容説明
学校の位置が80年代後半から大きく変わってきた。戦後の学校は、国家による直接的支配からの部分的民主化を遂げた。しかし、権力的なあるいは実務主義的な管理主義と、戦後登場した能力主義との2つの統制原理によって、学校は浸食され続けた。これまで、この2つの統制原理をめぐって、学校制度や教育内容と教育方法が議論されてきたのである。しかし、今や、こうした対抗関係自体が、社会的変化の下で変貌を遂げている。それは、能力主義は多元的能力主義に、管理主義は規範主義的統制の様相を強めている。ここで規範主義的統制というのは、一定の秩序へと精神と身体を統合しようとする言説や行為をさしている。いずれも、かつての直截な統制ではなくソフトな顔つきをしているが、いつも強面を裏に潜ませており、閉塞観やストレスを生みだしている。本書は、こうした統制の現状を越えていく教育の営みを探ることが基本的な課題である。
目次
多線型学校の誕生
教育課程審議会答申の基本問題
多文化的共通教養論
授業の転換―共同する社会科をめぐって
相互主体関係における指導性
学びへの参加権―教科指導の関係論的転換
歴史の学力形成と「自分の知識」―中学校歴史学習の課題
支配される学びと表現する学び
学びにおける明晰な政治
教科内容研究の真理性と政治性への転回
ディベート・発表学習・ワークショップ
総合学習の存在と教育課程づくり