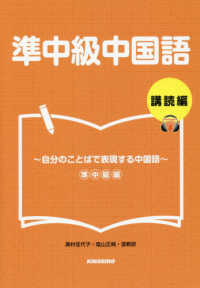出版社内容情報
【内容】
本書は、労働運動史を経済的階級関係である労使関係の歴史展開まで包含し、それらに規定された社会変動をも視野にいれた科学として構想した『労使関係の歴史社会学』(ミネルヴァ書房、1996年)の続編である。前著で提示した方法・理論の枠組みをもとに、グローバル・ジャパナイゼーション、ネオ・コーポラティズム、福祉国家、といった現代的論争に独自の視点から一石を投じ、提示する理論の妥当性、恒久性を追求する。必要に応じて前著の基本モティーフを解説しており、本書から前著にも進める構成となっている。
【目次】
まえがき
序論 本書の枠組と課題
1 「労使関係の歴史社会学」という試み
2 階級分析と歴史の説明
3 国家の形式と資本主義発展
4 NIEsの台頭と社会主義の崩壊
第1部 階級と歴史
1 階級関係は説明原理たりうるか
――階級分派・ジェンダー・エスニシティ
1 問題の所在
2 階級分派の概念的検討
3 階級分派と資本主義発展
4 結語
2 レギュラシオン学派の歴史認識
――「ポスト・フォーディズム」論争と「日本的特殊性」
1 問題の所在
2 日本的生産システムと「ポスト・フォーディズム」論争
3 「日本的特殊性」の根拠――レギュラシオン学派の歴史認識批判
4 結語
3 グローバル・ジャパナイゼーションは可能か
――「普遍性」と「特殊性」との相剋
1 問題の所在
2 日本的生産システムの存立機制
3 日本的生産システムの移転可能性
4 結語
第2部 社会変動と国家
4 ネオ・コーポラティズム概念は有効か
――日本におけるその適用可能性
1 問題の所在
2 ネオ・コーポラティズム概念の検討
3 ネオ・コーポラティズムのメカニズム
4 日本におけるネオ・コーポラティズム?
5 結語
5 福祉国家形成における差異と偏差
――何を差異とすべきなのか
1 問題の限定
2 福祉国家における「差異」
3 差異の発生メカニズム
4 具体的な差異と偏差の発生
5 結語
6 開発国家の社会的基礎
――国家の「相対的自律性」再考
1 問題の限定
2 国家と社会関係――「相対的自律性」再考
3 開発国家の社会的基礎
4 結語
第3部 世界システムの動態と趨勢
7 半周辺社会と後発性
――NIEs論としての日本主義論争
1 問題の所在
2 日本資本主義論争の経緯
3 NIEs論としての日本資本主義論争――一つの解釈
4 結語
8 半周辺社会の社会発展
――NIEs形成の社会的差異
1 問題の所在
2 NIEsにおける資本主義発展――類型転換の可能性
3 半周辺における差異――アジアとラテンアメリカ
4 結語
9 「ポスト新国際分業」の展開?
――日本企業の国際化戦略とアジアの資本主義発展
1 課題
2 枠組
3 分析
4 まとめ
10 世界システムと社会主義
――社会主義の解体は必然だったのか
1 問題の限定
2 世界システム論における社会主義
3 システム内社会主義の動態
4 結語
あとがき
参考文献
初出一覧
人名索引
事項索引
内容説明
本書は、労働運動史を経済的階級関係である労使関係の歴史展開まで包含し、それらに規定された社会変動をも射程にいれた科学として構想した『労使関係の歴史社会学』(ミネルヴァ書房・1996年)の続編である。前著で提示した方法・理論の枠組みをもとに、グローバル・ジャパナイゼーション、ネオ・コーポラティズム、福祉国家、といった現代的論争に独自の視点から一石を投じ、提示する理論の妥当性、恒久性を追求する。必要に応じて前著の基本的モティーフを解説しており、本書から前著にも進める構成となっている。
目次
第1部 階級と歴史(階級関係は説明原理たりうるか―階級分派・ジェンダー・エスニシティ;レギュラシオン学派の歴史認識―「ポスト・フォーディズム」論争と「日本的特殊性」 ほか)
第2部 社会変動と国家(ネオ・コーポラティズム概念は有効か―日本におけるその適用可能性;福祉国家形成における差異と偏差―何を差異とすべきなのか ほか)
第3部 世界システムの動態と趨勢(半周辺社会と後発性―NIEs論としての日本資本主義論争;半周辺社会の社会発展―NIEs形成の社会的差異 ほか)
-
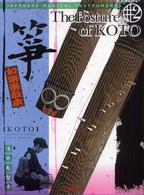
- 和書
- 箏 和楽器教本