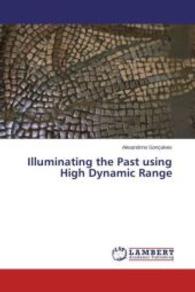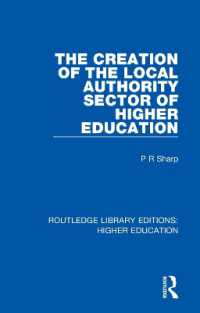出版社内容情報
【内容】
資本主義発達史の研究において,賃労働の生成史の究明が資本の生成史とならんで不可欠である。本書は,わが国ではややもすれば等閑視されがちな賃労働の生成を,イギリス産業革命の社会的側面から究明している。
【目次】
序章 産業革命に先行する経済の発展
第1章 綿工業における工場制度の成立と手織工の没落
第1節 綿紡績業における工場制度の成立
第2節 綿職布業における工場制度の成立
第3節 手織工の没落と工場労働者への転化
第2章 製鉄業・炭鉱業における技術革新と労働関係
第1節 製鉄業における技術革新と労働関係
第2節 炭鉱業における原生的労働関係の生成と消滅
第3章 産業革命期における賃労働の生成
第1節 議会囲込と賃労働の生成
第2節 産業革命期の労働移動
第4章 産業革命期における労働者の労働と生活
第1節 産業革命期労働者の消費生活と小売業
第2節 産業革命期の児童の雇用と日曜学校
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
シルク
7
名著だと思う。1985年刊ということで、割と古い本。「産業革命」「こども」という検索ワードで引っかかって、滋賀県立図書館で借りてきた。前半は、産業革命について、その時期の労働者全般について基本的なことがらを積み重ねていく感じ。中盤辺りから、俄然、「幼少年労働者」の「労働力陶冶」という話になっていく。「陶冶」ちゅーのは、教育学ではよう使われることばで、元来誰かのなかに具わっている、能力や才能を、心ゆくまで伸ばしてやることを言う。そんで産業革命期、児童労働が、国が急速に豊かになっていく、その歯車となったが→2025/09/17