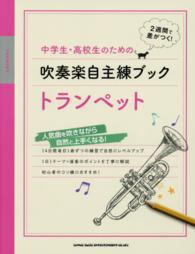出版社内容情報
「日本の自然」は自然の実態そのものではない。それは自然を表象したものであり、長い歴史のなかで文化的に構築されてきたものである。それはいかにしてつくられてきたのだろうか。
古代日本では稲こそが自然であり、収穫の秋はかなしみではなく喜びの季節だった。『万葉集』『古今和歌集』が育んだ四季概念。武士の枯山水。江戸時代の版画に描かれた富士山、水田、桜。こうした表象を「国有化」し、軍国主義に利用した近代。そして「自然」を消費する現代へ。
「自然」という作為を人類学の視座から描く。
【目次】
序章――人類学理論における「自然」
第一章 日本人の宇宙に住まう者たち
第二章 清らかな水田――奈良時代初期における「日本の自然」の誕生
第三章 農耕民族の四季から文化的に定義された四季へ――奈良時代と平安時代
第四章 「日本の自然」としての枯山水――中世
第五章 「日本の自然」としての水田、桜、富士山――江戸時代
第六章 「日本の自然」の国有化と軍事化――近代
第七章 「日本の自然」の家畜化・商品化
第八章 消費主義の文化的基盤
終章
あとがき
図版一覧
註
索引
内容説明
始源の稲。万葉歌の育む四季概念。それは平安の貴族文化で自然から離れ、枯山水の美学、文化的ナショナリズム、消費主義へ。自然の表象2000年史の人類学研究。
目次
序章 人類学理論における「自然」
第一章 日本人の宇宙に住まう者たち
第二章 清らかな水田―奈良時代初期における「日本の自然」の誕生
第三章 農耕民族の四季から文化的に定義された四季へ―奈良時代と平安時代
第四章 「日本の自然」としての枯山水―中世
第五章 「日本の自然」としての水田、桜、富士山―江戸時代
第六章 「日本の自然」の国有化と軍事化―近代
第七章 「日本の自然」の家畜化・商品化
第八章 消費主義の文化的基盤
終章
著者等紹介
大貫恵美子[オオヌキエミコ]
神戸市生まれ。甲南小学校、甲南女子中学校・高等学校、津田塾大学卒業。1968年、ウィスコンシン大学人類学博士号取得。ウィスコンシン大学ウィリアム・F・ヴィラス研究専任教授。アメリカ学士院正会員(1999年より)。La m´edaille du Coll`ege de France(2014年)。瑞宝中綬章(2020年)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kenitirokikuti
jackbdc
ちり
takao