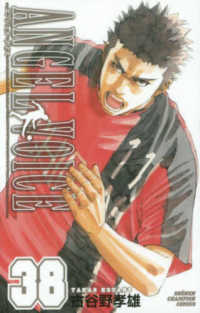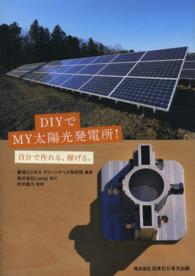出版社内容情報
レヴィ=ストロースは、マルクスの有名な定式〈人間は自分の歴史をつくる。けれども歴史をつくっていることを知らない〉を引用し、前半の言葉で歴史学を、後半の言葉で民族学を正当化し、二つのアプローチは補完的で分ちがたいものであることを示しているといい、人類学の目的は、意識されない思惟の普遍的構造を明らかにし、人間への全体的考察に寄与することにあると述べている。
この目的を果すために、無意識な言語活動に音韻上の体系をもたらした構造言語学の成果や数学の変換理論を人類学に適用することは、レヴィ=ストロースによりはじめて、ひとつの力をもった方法として確立した。本書は、未開社会の親族関係、社会組織、宗教、神話、芸術に構造分析の軌跡を具体的に例示した、構造主義人類学のマニフェストというべき画期的論文集。後半の諸章における人類学の方法と人類学教育の現状と未来についての考察も、きわめて示唆に富むものである。
〈レヴィ=ストロースは、創造的芸術家や精神分析の冒険者と同じ精神行為を内包する、トータルな仕事としての人類学を創造した。〉(スーザン・ソンタグ)
内容説明
構造言語学を人類学に適用し、親族関係、社会、宗教、神話、芸術を分析する。構造主義人類学のマニフェストであり、画期的な論文集。
目次
歴史学と民族学
言語と親族(言語学と人類学における構造分析;言語と社会;言語学と人類学;第3章、第4章への後記)
社会組織(民族学におけるアルカイスムの概念;中部および東部ブラジルにおける社会構造;双分組織は実在するか)
呪術と宗教(呪術師とその呪術;象徴的効果;神話の構造;構造と弁証法)
芸術(アジアとアメリカの芸術における図像表現の分割性;魚のつまった胴体をもつ蛇)
方法と教育の諸問題(民族学における構造の観念;第十五章への追記;社会科学における人類学の位置、および、人類学の教育が提起する諸問題)
著者等紹介
レヴィ=ストロース,クロード[レヴィ=ストロース,クロード] [L´evi‐Strauss,Claude]
1908‐2009。ベルギーに生まれる。パリ大学卒業。1931年、哲学教授資格を得る。1935‐38年、新設のサン・パウロ大学社会学教授として赴任、人類学の研究を始める。1941年からニューヨークのニュー・スクール・フォー・ソーシャル・リサーチで文化人類学の研究に従事。1959年コレージュ・ド・フランスの正教授となり、社会人類学の講座を創設。1982年退官。アカデミー・フランセーズ会員
荒川幾男[アラカワイクオ]
1926年生。東京大学文学部哲学科卒業。元東京経済大学教授。2005年歿
生松敬三[イケマツケイゾウ]
1928年生。東京大学文学部哲学科卒業。元中央大学教授。1984年歿
川田順造[カワダジュンゾウ]
1934年生。東京大学教養学部教養学科卒業。現在東京外国語大学名誉教授・日本常民文化研究所所員
佐々木明[ササキアキラ]
1934年生。東京大学教養学部教養学科卒業。青山学院大学名誉教授。2010年歿(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 【単話版】僕は今すぐ前世の記憶を捨てた…
-

- 電子書籍
- 流星はヌードをまとう 3 ジュールコミ…