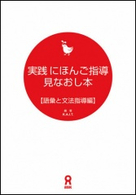出版社内容情報
「本書は、悪い習慣を直すための「簡単なコツ」を紹介したりするものではない。むしろ、他の本で紹介されている習慣を変えるための魔法のような解決策のほとんどが、本物の科学の前では意味をなさなくなることを明らかにしていく。……行動を変えやすくするための、科学的な裏付けのあるアイデアも得られるはずだ」(本文より)
過食やスマートフォンの使いすぎから、飲酒や喫煙、果ては依存性のある薬物の使用まで、一度習慣づいた行動をやめたくてもやめられずにいる人は多い。一方私たちは、交通ルールや道具の使い方、毎日のルーチンなどが習慣になっているおかげで、いちいち立ち止まって考えずに行動できている。本書では、こうした習慣のありようを最新の科学的知見に基づいて定義づけ、その詳細に立ち入っていく。
全二部構成の第I部では、習慣的行動の性質やその形成メカニズムを脳神経科学や心理学に基づいて解説する。第II部では、習慣を変えるための裏付けある方法や、応用の見込みのある研究成果を紹介する。
著者は、再現性と透明性の高い科学研究を目指す、オープンサイエンス運動をリードする認知神経科学者である。科学界における「再現性の危機」の先を見据えた研究を通して綴られる、習慣の実像。
内容説明
過食やスマートフォンの使いすぎから、飲酒や喫煙、果ては依存性のある薬物の使用まで、一度習慣づいた行動をやめたくてもやめられずにいる人は多い。一方私たちは、交通ルールや道具の使い方、毎日のルーチンなどが習慣になっているおかげで、いちいち立ち止まって考えずに行動できている。本書では、こうした習慣のありようを最新の科学的知見に基づいて定義づけ、その詳細に立ち入っていく。全二部構成の第1部では、習慣的行動の性質やその形成メカニズムを脳神経科学や心理学に基づいて解説する。第2部では、習慣を変えるための裏付けある方法や、応用の見込みのある研究成果を紹介する。著者は、再現性と透明性の高い科学研究を目指す、オープンサイエンス運動をリードする認知神経科学者である。科学界における「再現性の危機」の先を見据えた研究を通して綴られる、習慣の実像。
目次
第1部 習慣の機械―なぜ人は習慣から抜け出せないのか(習慣とは何か?;脳が習慣を生み出すメカニズム;一度習慣化すれば、いつまでも続く;「私」を巡る闘い;自制心―人間の最大の力?;依存症―習慣が悪さするとき)
第2部 習慣を変えるには―行動変容の科学(新しい行動変容の科学に向けて;成功に向けた計画―行動変容がうまくいくための鍵;習慣をハックする―行動変容のための新たなツール;エピローグ)
著者等紹介
ポルドラック,ラッセル・A.[ポルドラック,ラッセルA.] [Poldrack,Russell A.]
スタンフォード大学心理学部教授。イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校にてPh.D.を取得。2014年より現職。人間の脳が、意思決定や実行機能調節、学習や記憶をどのように行っているのかを理解することを目標としている。計算神経科学に基づいたツールの開発や、よりよいデータの解釈に寄与するリソースの提供を通して、研究実践の改革に取り組んでいる
神谷之康[カミタニユキヤス]
京都大学大学院情報学研究科・教授、ATR情報研究所・客員室長(ATRフェロー)。専門は脳情報学、奈良県生まれ。東京大学教養学部卒業。カリフォルニア工科大学でPh.D.取得。機械学習を用いて脳信号を解読する「ブレイン・デコーディング」法を開発し、ヒトの脳活動パターンから視覚イメージや夢の解読することに成功した。SCIENTIFIC AMERICAN誌「科学技術に貢献した50人」(2005)、塚原仲晃賞(2013)、日本学術振興会賞(2014)、大阪科学賞(2015)。アーティストとのコラボレーションも行う
児島修[コジマオサム]
英日翻訳者。1970年生。立命館大学文学部卒(心理学専攻)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
ばんだねいっぺい
buuupuuu
taku
いぬ
-
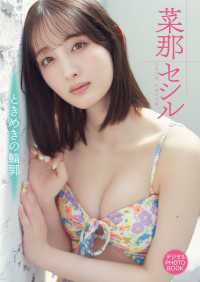
- 電子書籍
- 【デジタル限定】菜那セシル デジタルP…
-
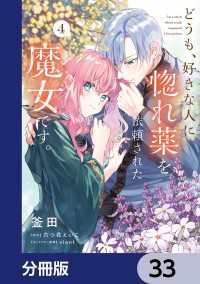
- 電子書籍
- どうも、好きな人に惚れ薬を依頼された魔…
-

- 電子書籍
- ふくふくごはん(分冊版) 【第12話】…
-

- 電子書籍
- 転生先は回復の泉の中~苦しくても死ねな…