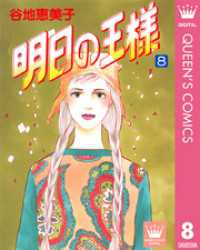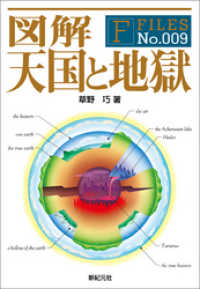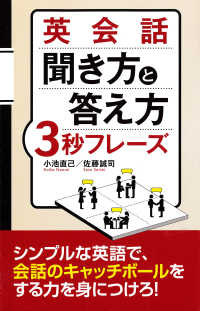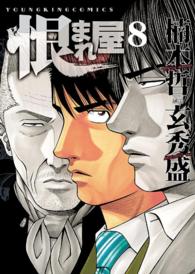- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 図書館・博物館
- > 図書館・博物館学その他
出版社内容情報
〈本書を通じて目指したのは、なんらかの本質を持つようなアーカイブなるものが自己実現するという進歩史観的な歴史像を提示することではない。むしろ、雑多な思想や制作や営為が合流した結果として、わたしたちが現在のデジタル時代のアーカイブを想像できるようになっていることを示そうとした。複雑なアーカイブという現象を、単純化したモデルとして提示するのではなく、むしろ個々の事例に即して解像度を上げて理解しようと試みたのである〉
デジタルアーカイブの定義の変遷から、文書をデジタル化する意味と問題、保存と活用の現状、博物館・図書館・文書館を貫く効用と課題、自治体史や研究者資料における役割、サブカルやユーチューブと著作権問題、複製技術の歴史など、気鋭の研究者11名による論考を収録。デジタル時代の今日において「アーカイブ」と呼ばれるものに合流してきたさまざまな系譜を歴史的に明らかにするとともに、それが社会に作用する仕方の見取り図の全貌を示す。
内容説明
デジタルアーカイブの定義の変遷から、文書をデジタル化する意味と問題、保存と活用の現状、博物館・図書館・文書館を貫く効用と課題、自治体史や研究者資料における役割、サブカルやユーチューブと著作権問題、複製技術の歴史など、気鋭の研究者11名による論考を収録。デジタル時代の今日において「アーカイブ」と呼ばれるものに合流してきたさまざまな系譜を歴史的に明らかにするとともに、それが社会に作用する仕方の見取り図の全貌を示す。
目次
序章 デジタル時代のアーカイブの諸系譜をたどるために
第1部 アーカイブの系譜を解きほぐす(アーカイブの概念史;アーカイブの技術史;博物館・図書館・文書館から見たアーカイブ史)
第2部 多様なアーカイブの文脈を紐解く(自治体史とデジタルアーカイブ;研究者から立ちあがるアーカイブ;文化活動の側面を持つアーカイブ―祭の記録から動画投稿まで)
第3部 アーカイブをメディアとして読み解く(複製技術とアーカイブ―日本における文書複製・保存技術の歴史的系譜;デジタルテキストのメディア特性;コミュニティの想像とアーカイブ)
終章 まとめと展望
著者等紹介
柳与志夫[ヤナギヨシオ]
東京大学大学院情報学環特任教授。デジタルアーカイブ論。1954年生まれ。慶應義塾大学文学部卒業。主要業績『デジタルアーカイブの理論と政策―デジタル文化資源の活用に向けて』(頸草書房、2020年、デジタルアーカイブ学会第3回学会賞学術賞(著書)受賞)ほか
加藤諭[カトウサトシ]
東北大学学術資源研究公開センター史料館准教授。歴史学・アーカイブズ学・デジタルアーカイブ。1978年生まれ。博士(文学)。東北大学大学院文学研究科博士後期課程修了
宮本隆史[ミヤモトタカシ]
大阪大学大学院人文学研究科講師。歴史学・南アジア史・デジタルアーカイブ。1979年生まれ。修士(学術)。東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。