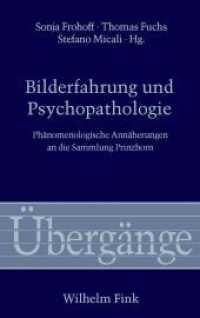出版社内容情報
日本とロシアの首脳のあいだで「北方領土問題」が議論される。しかし「北方領土」とは誰のためのものなのか。北方領土と呼ばれる島々や、かつては樺太という名だった現サハリンの住民は、二つの巨大国家の交渉を、どのように考えるのだろう。本書は、アイヌを中心に、日本とロシアという国家が先住民族を同化・差別化してきた歴史を詳細に追いながら、辺境という視座から、われわれの「いま」と「今後」を考える。
「植民地時代の探検家たちがおこなった旅は、帝都の中心から出発し、外に向かい、〈奥地〉にまでいたるものだった。彼らは、植民地支配をおこなう社会の物理的な武器ばかりでなく、知的な武器をも携えて、一つひとつ道を切り拓き、商人、入植者、伝染病がその後を追った。旅から持ち帰ったのは大量の原材料であった。鉱物のサンプル、民族誌学的〈骨董品〉、地図、未知の人びとの話、これらはやがて植民地支配権力がもつ拡張する知識体系のうちに編入されていった。本書でおこないたいのはこの過程を転倒する作業である。〈奥地〉の心臓部から、外に向かい、国家/国民的およびグローバルな帝都にまでいたり、帝都型思考様式を新たに問い直す方法を持ち帰る、そのような旅路への出発である」
著者はオーストラリア在住の気鋭の日本研究者。現代思想や近現代史・アイヌ問題など、その緻密な考察と開かれた問題提起は、じつに鮮やかである。戦前に樺太に住んでいた人たちとともにサハリンに向かう終章の紀行文もまた、みごとだ。
内容説明
日本とロシアは、アイヌなどの先住民族をどのように国家に組み込んできたのか。辺境という視座からの試み。
目次
序 辺境から眺める
第1章 フロンティアを創造する―日本極北における国境、アイデンティティ、歴史
第2章 歴史のもうひとつの風景
第3章 民族誌学の眼をとおして
第4章 国民、近代、先住民族
第5章 他者性への道―二〇世紀日本におけるアイヌとアイデンティティ・ポリティクス
第6章 集合的記憶、集合的忘却―先住民族、シティズンシップ、国際共同体
終章 サハリンを回想する
著者等紹介
モーリス=鈴木,テッサ[モーリススズキ,テッサ] [Morris‐Suzuki,Tessa]
1951年生まれ。オーストラリア国立大学名誉教授。専攻は日本経済史、思想史
大川正彦[オオカワマサヒコ]
1965年生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科博士後期課程単位取得退学。政治学専攻。現在、東京外国語大学総合国際学研究院教授。修士(政治学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やいっち
瀬希瑞 世季子