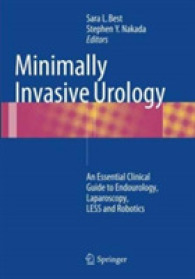出版社内容情報
暴力と、暴力があったことを黙らせる力は一緒になっている。セクハラの被害にあったとき、その場で何も言えなくさせ、その後に沈黙させ、言えば非難にさらされる、その力はどう働いているのだろう。私たちはなぜ「たいしたことではない」と、その場を丸くおさめてしまうのだろう。#metooで語られた多くの声は、変化するための新たな知覚をみせてくれる。私たちのものの見方、言葉、その共有のしかたを考え、小さな声で世界を変えていくエッセイ。
内容説明
#MeToo運動は、社会が変化する可能性を開いてくれた。暴力を支える論理を問い直し、新たな言葉、イメージ、その共有のしかたを考える。小さな声で世界を変えていく一冊。
著者等紹介
エムケ,カロリン[エムケ,カロリン] [Emcke,Carolin]
ジャーナリスト。1967年生まれ。ロンドン、フランクフルト、ハーヴァードの各大学にて哲学、政治、歴史を専攻。哲学博士。『シュピーゲル』『ツァイト』の記者として、世界各地の紛争地を取材。2014年よりフリージャーナリストとして多方面で活躍。『メディウム・マガジン』にて2010年年間最優秀ジャーナリストに選ばれたほか、レッシング賞(2015年)、ドイツ図書流通連盟平和賞(2016年)をはじめ受賞多数
浅井晶子[アサイショウコ]
翻訳家。1973年生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程単位認定退学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ケイトKATE
21
性的虐待を受けた被害者の声が届くには何が必要か。加害者側にある支配の構造はどのようなものか。カロリン・エムケはモノローグ形式で考察している。エムケ自身、同性愛者であるためマイノリティーとしての視点があり、性的虐待の問題について細かい所まで目が届いている。そして、性的虐待の原因となっている男性中心社会や異性愛至上主義への論理を冷静沈着な言葉で看破する文章は痛快である。2020/12/11
きゅー
8
2017年に突如して広まったMeToo運動に対して、エムケは沈黙をしていた。それは、彼女が同性愛者であり、いかなる立場から自分が発言を行うべきか悩んでいたからだという。 本書の冒頭で彼女は、ためらいがちに「つぶやくように書く。小声で、他者に向けるより前に、まずは自分ひとりに向かって。」と書いている。そしてこれまで自分が目にした差別、暴力を言葉にする。当時の自分の感情を思い出し、その際の自身の行為を(あるいは行為のなさを)意味づけようとする。2022/02/08
Olive
6
#MeToo議論には二種類のいわれなき想定がある。 その1・他者の体験は追体験することができない。理解することができないというもの。これは差別される側を学ぼうとすること。その2・体験したことのない人間は語るべきではないというもの。構造的人種差別に対して白人が、同性愛者に対して異性愛者が等. 欲望の対象を決定する権利は自分だけが持っているものだ。自分たちの権力を過小評価するべきではないと。自分は無力だと考えてはいけない。というのが大筋。2020/12/12
林克也
4
カロリン・エムケの本、なぜか読んでしまう。日本語版3冊とも読んだが、毎回読後にゾワゾワした気持ちになってしまう。 今回の本は、訳者の浅井さんの「今度は別の凝り固まった構造となり、誰かを抑圧し、差別し、排除することがないか、常に自省し続けなければならないと強く思う」という言葉に一番強く同意した。しかし、今の日本の政治屋とそれを操る連中に対して、こういう見方で接する・見つめることが、はたして自分にできるだろうか・・・。 2020/11/17
Yoshiko
2
2017年に始まった#MeToo運動を受けて、エムケが翌年に行った朗読パフォーマンスをもとにしたエッセー。個人的な体験を掘り下げつつ、この社会に差別と性暴力が蔓延しているのに沈潜しているのはなぜかを探求している。それは、だれかを指弾すればすむわけではない。自分自身もその構造の一部であり、時に被害を受け、時には加害構造を支える側に回る。 フーコーの権力論を下敷きにしているのだが、本書を読んで改めて思ったけれど、権力(英語だとパワー)を日本語にするとき「権力」とすると限定された意味になってしまう。要検討。2022/04/05
-

- 電子書籍
- 酒と鬼は二合まで【単話】(35) やわ…
-

- 和雑誌
- ふらんす (2025年11月号)