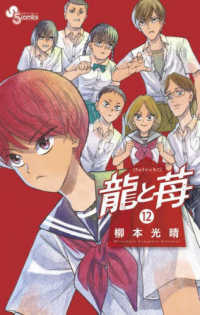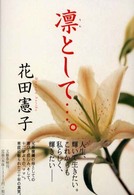出版社内容情報
アメリカが世界の覇権を握り、新しい国際秩序を形成したことの影響を、日本ほど深く受けた国はない。日米のこの特異な関係を、ジョージ・ケナンは「不自然な親密さ」と呼んだ。
英国から独立を勝ち取り、自由主義を礎に建国された移民の国アメリカ。彼らアメリカ人が西にフロンティアを広げ、さらに太平洋の向こう側で遭遇した日本は、2000年もの間移民を知ることなく、自民族の共同体を重んじてきた保守的社会だった。やがてこの対照的な2か国は、太平洋をはさんで野心的な新興国として頭角を現す。日米戦争の起源である。
アメリカはこの戦争を、日本を完全に敗北させるための戦いと位置づけ、無条件降伏政策を追求した。敵国を軍事的に破るだけでなく自国に似せて改造するというのは、戦争の目的として未曾有のことだった。この野心的な政策が、戦争の趨勢と戦後の日本社会を規定することになる。それは日本の民主化を短期的には進めたが、決定的には困難に陥れ、対米従属と自国アイデンティティの両立という不可能を前に、日本は深刻な矛盾に陥る。
本書はアメリカの世紀を生きた日本を、政治、経済、社会、法律、精神という多方位から容赦なく描き出した。少しの希望とともに――。アメリカの世紀が暮れ始めた今、日本はどこへ向かうのか。米国きっての日本研究者による、痛切な日本現代史。
内容説明
米国と密接で特異な関係を結んだ敗戦国日本。この国は無条件降伏政策の呪縛と米国覇権の時代をどう生きたのか。日米関係の過酷な鏡が映し出す、現代日本の姿。
目次
序―不自然な親密さ
第1章 二つの新興国
第2章 無条件降伏政策
第3章 原爆使用の決定
第4章 米国人の手になる革命
第5章 日本の従属
第6章 日本人の魂を賭けて
第7章 奇妙な同盟
第8章 競合する資本主義
第9章 欧米モデルに収まらない日本社会
第10章 日本の民主主義
第11章 暮れゆく米国の世紀と日本
著者等紹介
パイル,ケネス・B.[パイル,ケネスB.] [Pyle,Kenneth B.]
ワシントン大学歴史学部および同大学ヘンリー・M.ジャクソン国際研究所名誉教授。日本研究の主要ジャーナルJournal of Japanese Studiesを創刊。長年にわたりワシントン大学ヘンリー・M.ジャクソン国際研究所長の任にあり、全米アジア研究所も設立、所長を務める。1999年に勲四等旭日中綬章を受章
山岡由美[ヤマオカユミ]
津田塾大学学芸学部国際関係学科卒業。出版社勤務を経て翻訳業に従事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
koji
BLACK無糖好き
Mc6ρ助
hana87
色々甚平