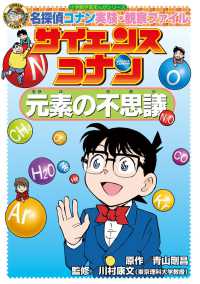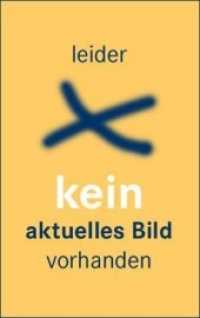出版社内容情報
現在まで「触れたくない敗戦史」ゆえに放置されてきた「日ソ戦争」(1945.8.9-9.2)の詳細を初めて描く。「日ソ戦争」はソ連軍170万、日本軍100万が短期間であれ戦い、死者は将兵約8万、居留民約18万、捕虜約60万を数えた、明らかな戦争であった。旧ソ連の公文書や日本側資料、既存の研究を駆使し、軍事的側面に力点を置きながら、この戦争の実像および米ソの関係、戦後にもたらした重い「遺産」について考察する。
内容説明
「触れたくない敗戦史」ゆえに放置されてきた日ソ戦争(1945.8.9‐9.2)の戦闘の詳細と全体像はいかなるものであったか。敗戦後75年目に初めて明らかになる真実。
目次
第1章 戦争前史―ヤルタからポツダムまで(ソ連の外交と対日戦準備;日本の外交と対ソ戦準備;日ソ戦争における米国要因)
第2章 日ソ八月戦争(ソ連軍の満洲侵攻と関東軍;ソ連軍による満洲での蛮行;捕虜の留置から移送へ)
第3章 戦後への重い遺産(満洲「残留」と「留用」;捕虜と賠償をめぐる米ソ論争;ソ連の「戦犯」裁判)
著者等紹介
富田武[トミタタケシ]
1945年福島県生まれ。東京大学法学部卒業。成蹊大学名誉教授。ロシア・ソ連政治史、日ソ関係史、シベリア抑留(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ケイトKATE
25
1945年8月8日に始まったソ連の対日参戦。短期間で終わったこともあり、あまり取り上げていなかったが、本書ではロシア側のソ連時代の史料も参考にして戦争の内容を追っている。日ソ戦争はソ連軍の兵力、兵器共に日本軍を圧倒した。それにしても、日本はソ連をあらゆる面で甘く見ていた。アメリカやイギリスと同盟を結んでナチス・ドイツと戦っている時点で、いずれは日本に攻撃する可能性は大きかったはずである。日ソ戦争によって中国残留孤児やシベリア抑留といった大きすぎる代償を負ったことを見れば、早く戦争を止めるべきだった。2025/08/19
Toska
9
語られることの少なかった戦争を、日ソ双方の史料を突き合わせて丹念に追いかけた労作。「参謀の戦史」から「兵士の戦史」へという志が述べられているが、そもそも日ソ戦については「参謀の戦史」すらろくに書かれてこなかったのが実情で、本書の持つ意味は極めて大きい。国の指導部から一兵卒や難民に至るまで、何を考えどのような経験をしたかが活写されている。巻末の「文献一覧と一部解題」も、今現在どのような史料や文献が利用できるかを簡潔にまとめたものとして重要。2022/05/16
みさと
8
伯父の一人はレイテで自決し一人はシベリアに抑留された著者が、執念を持って日露の史料を渉猟して描き出す日ソ戦争史。ソ連側の戦略・外交はいかなるものであったか、それに対する日本と関東軍の実態はいかなるものであったか。日本軍とソ連軍の兵士はどのような思いで戦ったのか、満蒙開拓団や居留民の実情はどうだったのか。大岡昇平の『レイテ戦記』を想起させるような、兵士の戦史を個人名・部隊名にこだわって詳述していく。最前線の兵士や開拓団・居留民を棄て、戦略もなくただ自分たちだけ撤退した関東軍。日本とは一体何だったのだろうか。2021/06/10
あつもり
6
各戦闘の日ごとの局面を日ソの記録から追いかける研究書であり、一つずつの事実の重みに思いを馳せると到底読み進めることはできず、取りあえず一通り目を通しただけ、となりました。「関東軍がソ連参戦の報に接するや軍人、官吏、満鉄等の家族を優先的に列車で南方に移送するに至っては、『持久戦』とは『消極的応戦』による降伏引き延ばし策、ひいては『棄兵・棄民』の隠れ蓑だったと指弾されても仕方あるまい。」(P.5)関東軍死者8万人、捕虜59万人、民間死者24万人。なぜ避けられなかったのか、という思いが強く残ります。2021/04/04
晴天
6
断片的な情報やそれに基づくイメージばかり語られがちな1945年8月におけるソ連軍満州侵攻について、日ソの公的資料や手記回想録などから全体像を導き出す。装備人員の質量ともに圧倒的な差のある一方的な戦闘、それでも見せる頑強な抵抗、巻き込まれる民間人などの様相は凄惨という他なく、そこに至る失策や無策には憤りを禁じ得ない。個人的には、ハルビン学院や東京外国語学校出身のロシア語の心得のある人間が交渉に当たろうとしたりもするが、特に反応もなく銃火に倒されたり、あるいはスパイとして長期抑留されたりするのもやるせない。2020/08/11