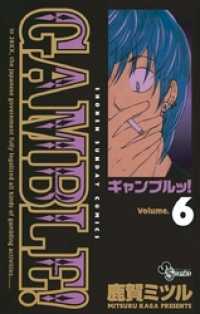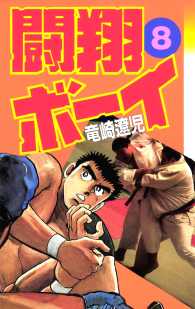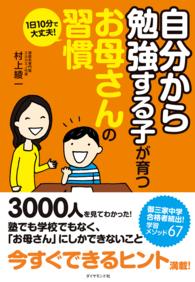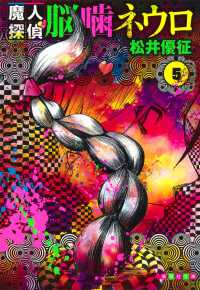出版社内容情報
『最底辺の10億人』のグローバルな視点から、リスクと便益の両方を見すえたモデルを提示。「この議論の多い問題について、あらゆる立場のあらゆる人への必読書だ」パットナム。
内容説明
『最底辺の10億人』のグローバルな視点から、コストと便益の両方を見すえた、モデルを提示。“移民自身”“受入国の住民”“送出国に残された人々”という三つの立場にバランスよく目配りしつつ、移住のグローバルな経済的、社会的、文化的影響を分析する。
目次
第1部 疑問と移住プロセス(移民というタブー;移住はなぜ加速するのか)
第2部 移住先の社会―歓迎か憤りか?(社会的影響;経済的影響 ほか)
第3部 移民―苦情か感謝か?(移民―移住の勝ち組;移民―移住の負け組)
第4部 取り残された人々(政治的影響;経済への影響 ほか)
第5部 移民政策を再考する(国家とナショナリズム;移民政策を目的に合致させる)
著者等紹介
コリアー,ポール[コリアー,ポール] [Collier,Paul]
オックスフォード大学ブラヴァトニック公共政策大学院経済学および公共政策教授。専門は開発経済学。内戦の因果、援助の効果、低所得国の民主主義、天然資源、都市化を研究している。1998‐2003年には世界銀行の研究開発部門ディレクターを務めた。現在、パリ政治学院客員教授、国際成長センターのディレクターも務める
松本裕[マツモトユウ]
翻訳家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
魚京童!
23
まず国に縛られてるよね。国があるから移民ができる。国の民が移動するだけだからね。でも住みたいところに昔から住んできたし、そこに邪魔者がいれば、排除してきた歴史がある。国なんてまやかしだよ。お金が儲かるところに移動する。だってここじゃ暮らせないんだもん。でも国があると、ここに住みなさいって言われる。間違ってるよね。移動手段が昔は歩くしかなかったけど、今は飛行機があるしね。世界はどんどん変わっていく。もう国なんていらないんじゃない?共同体を維持するために税収を取るのは理解できるけど、共同体を維持する国という制2019/10/05
トッシー7
4
日本は高齢化社会が益々進むから移民を受け入れた方がいいとの議論を聞くが、そんないいとこ取りができるのだろうか? 貧困 ナショナリズム 人種差別 考えるためのキーワードが結構見つかる。2019/11/21
matsu
2
昨今世界的に移民の是非について議論されているが、受け入れ国民、移民、送り出し国の人々の3視点から経済的、社会的、文化的な側面において、議論している。 端的に言うと、急激な移民受け入れは、受け入れ国、送り出し国どちらにとってもマイナス面が多く、規制は必要になる。しかしながら適切な移民の受け入れは短期的な面だけでなく長期的にも社会にとって有益になる。2020/02/03
dm
1
移民の文化的差異が大きいほど、移住率の増加に伴う受入国側でのディアスポラ係数は高くなる(=吸収率が低い) ディアスポラ曲線は、吸収率を高めることで、高移住率と小ディアスポラの両方を手に入れ、結果として受入側の経済成長をもたらす。移住プロセスの早い段階で長期的な観点から移民政策を策定する必要があること、高技能労働者の受入は生産性を高め賃金押し上げ効果がある。少子高齢化におかる従属人口指数低下を目的とした技能低水準移民受入はやってはいけない(技能低水準移民は扶養家族が多い傾向にあり、従属人口指数が高い)2025/04/28
林克也
1
「移民は世界をどう変えつつあるのか」というサブタイトル通り、途中経過の報告書。各種データや論考を羅列してあっても、それでどうなるのか、どうすることがいいのかは判らない。それを頼りに自分の頭で考えよ、ということなのだろうが、私の頭の中の消化酵素が上手く働かず消化不良で胸焼け(頭焼け?)してしまった。2020/05/05