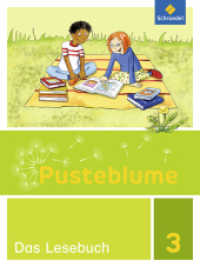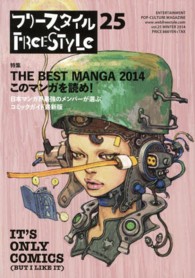出版社内容情報
食と国土を支える農家の危機が続く。持続可能な地域・農業・食料・エネルギー利用の具体的な政策とアジアと連携する環境共同体構想。日本人の生存と日本列島を支えてきたなりわい=農家が危機にある。1960年から2015年にかけて、農家戸数は600万戸から200万戸に減少し、作付け面積は半減した。農山村では集落の衰退と里山の荒廃が進む。米国のTPP撤退後も、政権はNAFTA-TPP型の推進と農業の成長産業化・企業化をめざしている。本書は、米国流グローバリズムに組み込まれず、地方の「自治力」を高めた骨太で具体的な農業・食料・エネルギー政策を示す。
まえがき
序 論 いま、なぜ自然資源経済論か
?部 歴史的な岐路に立つ農業・農山村
第一章 農業・農山村危機の実像とその背景
第二章 これからの農業・農山村政策
第三章 人間と自然資源のかかわりを再構築する基礎
?部 世界の中の自然資源経済
第四章 条件不利な農業・農山村を支える仕組み──EUとオーストリア
第五章 農村景観・農村文化の価値保全
第六章 農山村地域からのエネルギー転換
第七章 貿易と経済連携への新視角――東アジア地域との共生へ
終 章 農業の担い手をどう支えていくか
あとがき
寺西俊一[テラニシシュンイチ]
著・文・その他/編集
石田信隆[イシダノブタカ]
著・文・その他/編集
山下英俊[ヤマシタヒデトシ]
著・文・その他/編集
内容説明
日本の食と自然・風土を支えてきた農家が歴史的な岐路に立つ。持続可能な農業・食料・エネルギー利用の仕組みを、アジアと連携し発展する環境共同体につなぐ道。
目次
いま、なぜ自然資源経済論か
1 歴史的な岐路に立つ農業・農山村(農業・農山村危機の実像とその背景;これからの農業・農山村政策;人間と自然資源のかかわりを再構築するために)
2 世界のなかの自然資源経済(条件不利な農業・農山村を支える仕組み―EUとオーストリア;景観・文化の保全―かけがえのない価値を守る仕組み;農山村地域からのエネルギー転換;貿易と経済連携への新視角―東アジア地域との共生へ)
自然資源経済の担い手をどう支えていくか
著者等紹介
寺西俊一[テラニシシュンイチ]
1951年石川県鶴来町(現白山市)生まれ。帝京大学経済学部教授。一橋大学名誉教授。京都大学経済学部卒。一橋大学大学院経済学研究科博士後期課程単位取得退学。専門は環境経済学・環境政策論。2009年度から一橋大学・自然資源経済論プロジェクト代表。この間に、環境経済・政策学会会長、日本環境会議理事長、日本学術会議連携会員、『環境と公害』(岩波書店)編集代表なども務める
石田信隆[イシダノブタカ]
1949年京都府峰山町(現京丹後市)生まれ。農林中央金庫および株式会社農林中金総合研究所勤務を経て同客員研究員、一橋大学経済学研究科客員教授。京都大学経済学部卒。専門は農業経済学・協同組合論。グローバル化進展下の農業・農政・農協を研究。日本環境会議理事、国際アジア共同体学会理事
山下英俊[ヤマシタヒデトシ]
1973年長野県長野市生まれ。一橋大学大学院経済学研究科准教授。東京大学教養学部卒。東京大学大学院総合文化研究科博士課程中退。博士(学術)。専門は資源経済学・環境経済学。「再生」と「循環」をキーワードとし、地域レベルで持続可能な社会の構築を模索している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
chuji
くさかんむり
にわ
キャド兄さん